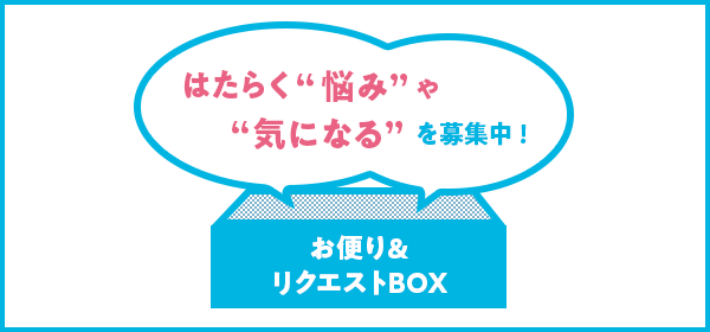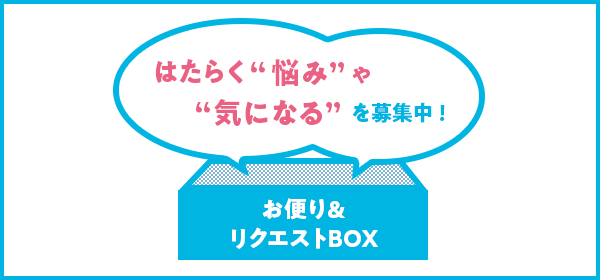- TOP
- WORK LIFE THEATER
- なぜオウム真理教に密着できたのか。自分の視点を貫くドキュメンタリー作家 森達也の生き方
なぜオウム真理教に密着できたのか。自分の視点を貫くドキュメンタリー作家 森達也の生き方

この世界には、さまざまな「真実」があります。マスメディアから得られる情報によって、私たちはその「真実」を理解したと思い込みがちですが、私たちが見えているのは「真実」のほんの一片にすぎません。マスコミの伝え方や世論によって、歪曲された「真実」が広まってしまうこともあり得るのです。
そんな「真実」の受け取り方に警鐘を鳴らしているのが、ドキュメンタリー映画監督の森達也さん。監督業をしながら、明治大学の特任教授としても若い世代にメディアリテラシーを教えています。
そんな森さんの“上手くいかなかった”若手時代から、ドキュメンタリーを撮り始めるまで、そして、今この時代にメディアに対して思っていることなどを語っていただきました。
大学卒業後、職を転々とした不安定な日々

立教大学に進学し、映画研究会で映像を撮りながら、劇団で芝居をする日々を過ごした森さん。「就職に対するリアリティがなかった」ことから、そのまま所属していた新劇の養成所に通い、新劇俳優を目指していました。先輩や友人のツテをたどり、大衆演劇や自作映画に出演する日々。もちろん収入はほぼなく、アルバイトで食いつないでいたといいます。
転機となったのは29歳のとき。結婚を機に「このままじゃまずいな」と新聞の求人で見た小さな広告制作会社に就職し、サラリーマン生活をスタートさせましたが、1年と経たずに退職。その後、不動産会社や広告代理店など職を転々としていたのだそう。
「今よりも、『大卒はすぐ就職、そのまま定年まで勤めあげる』という意識がずっと強い時代でしたから。一度レールから外れてしまうと、もう戻れないという意識が自分も、周りも大きかったんです。自分自身は覚悟していたけれど、やっぱり怖いし、不安でした」
さまざまな会社ではたらいているうちに、「やっぱり学生のころから携わっていた映像をやりたい」という気持ちが大きくなった森さんでしたが、その時すでに年齢は30歳。若いうちから経験を積むことを求められる映画制作の世界は無理だろうと考え、テレビ番組制作の世界に飛び込みました。
ドラマが作れると思ったら、ドキュメンタリーの制作会社だった

「僕、まったくドキュメンタリーに興味がなかったんです」と切り出す森さん。
「学生のころも映画研究会や演劇研究会に入っていたので、『テレビ制作会社に入るのだからドラマを作りたい!』と意気込んで入ったんですけど……。入社してから『うちはドキュメンタリー番組しか作らないけど』と言われたんです」
当時は「失敗した!」と思ったそうですが、ちょうど同時期に第一子が誕生。辞めるわけにもいかず、しばらく続けることに。
ドキュメンタリーを面白いと感じたのは、入社直後、ADとしてタイ、香港と各国を周ったときのこと。実はこのロケが森さんにとって初めての海外渡航でした。
そんな初の海外で、香港を訪れた際、かつてあった九龍城の巨大スラム街に迷い込んでしまったそう。観光客が行くような場所ではなく、絶対に足を踏み入れてはいけないと噂される場所でしたが、実際に足を踏み入れてしまえば人々が当たり前の生活を送り、森さんたちを歓迎してくれたのだとか。
「ドキュメンタリーが面白いんじゃなくて、ドキュメンタリーを通じてできる体験が面白いと感じた」という森さんは、どんどんドキュメンタリーにのめりこんでいきます。
「台本通りに動く人間を撮影するドラマや映画と違って、まったく予期もせぬことが起こるドキュメンタリー。自分の予想を裏切るようなことが次々と起こるから、これは面白いんじゃないかと思いましたね。ただ、僕はもう年齢も年齢でしたから、『面白いから続ける』だけでやっていけるほど若くなくて、早く自分の企画を出して自分の番組をやらないといけないという焦りがありました」

ある程度AD業務に慣れたら、次に待ち受けるのは「企画を出す」というフェーズ。番組の制作を始めるには、制作会社社内の企画承認を経て、テレビ局のプロデューサーが首を縦に振らなければなりません。「本当にいろいろな企画を書いた」という森さんですが、なかなか社内の承認が下りず、悶々としているうちに時間だけが過ぎていきました。
「社内の承認が下りないんだったら、フリーになればいいんだと思って、実際に会社を辞め、フリーランスのディレクターとして仕事を始めました。自分で局に企画を持って行って通らないのであればあきらめがつきますが、僕はその前の制作会社の壁を超えることができていませんでしたから。ディレクターとかカメラマンとか、割とフリーで活動している人が多い業界なので、フリーになることに抵抗はなかったんですね。それでフリーになったら、自分で企画を通せるようになったんです」
大きな転機となった『A』の制作

森さんがフリーのディレクターのキャリアを歩もうとしていたちょうどそのとき、日本全国に大きなショックを与えた「地下鉄サリン事件」が発生。報道は朝から晩までオウム真理教を取り上げ、半年ほど新聞各紙の一面がオウム真理教に染まりました。
「スポーツ紙の一面から野球が消えたんですよ。スポーツ新聞なのに、スポーツを取り上げずにオウムを取り上げるという、とにかく異常なことが起きていました」
森さんが仕事をするテレビ業界も例外ではなく、必然的にオウム真理教に関する番組を作らざるを得ない状況にあったといいます。
「たとえば、ある人のドキュメンタリーを撮ろうと思ったら、その人にアポをとって、その人が仕事と仕事終わりに誰と会っているのか、休暇は何をして過ごしているのか、といったことを撮りますよね。だから、オウム真理教のドキュメンタリーを撮るなら、オウム真理教にアポをとって、信者の生活や施設内での行動や喜怒哀楽を撮るのが当たり前だと思ったんですよ。でも、僕以外に施設に入ってドキュメンタリーを作る人はいなかった」
当時、テロリスト集団と報道され、多くの人から批判の目を向けられたオウム真理教。メディアも、「オウム=絶対悪」という決めつけの元、報道が加熱していき、ときにはフェイクニュースが流れることもあったそう。その中で、オウムを批判するでもなく、ドキュメンタリーの対象としてオウム信者に内側からカメラを向け、報道されていない部分に目を向けようとする森さんの姿勢は「オウムを擁護している」と叩かれることも多かったんだとか。
施設など内部に足を踏み入れることに関しては、「まったく怖くなかった」という森さん。「九龍城に足を踏み入れた時のように、みんなが怖い、危ないと言っている場所は意外とそうではない」という経験があったからこそ、森さんに迷いはありませんでした。「実際に出会う信者は純朴で善良で世間知らずで。世間がイメージする血に飢えた獣みたいな人はいませんでした」と語る森さんですが、そもそもどうやって内部に足を踏み入れるまでの取材にこぎつけたのでしょうか。

問いを投げかけると、「手紙です」と一言。「手紙をオウム真理教の広報部に対して書きました。1回目は返事がなかったのですが、もう1回書いたらお返事をもらって、青山の本部に来てくださいと。後から『メディアの人から手紙をもらったのは初めてです』と言われ、心底びっくりしたのを覚えています」と森さん。当時、オウム真理教の広報部には取材依頼が毎日山のように届いていたといいますが、森さん以外は電話かファックスでの依頼のみ。今のようにメールが普及していない時代、森さんからの手紙はオウム真理教側に心を開かせるきっかけになったのかもしれません。
『A』を公開した森さんに対し、オウム真理教に対する強いコネクションがあったのではとか、根性ある取材といった声も多く寄せられたそうですが、森さんは「普段自分がやっていることをそのままやっただけ」と一蹴。「特別な手法など何もないですよ」と当時を振り返っていました。
「ドキュメンタリーは主観でいい」

ディレクター時代、先輩たちから叩き込まれたのは「公正・中立・客観的」というドキュメンタリーの作り方。
しかし、「『A』を撮る過程で、主観でいいんだって気付いた」そうです。自分でカメラを回し、今このフレームを自分で選んで撮る、自分で選んでズームする、その撮った映像を自分で編集して、場合によっては音楽を付ける。その制作過程に、客観性が存在しないことに気付きます。
「ドキュメンタリーって自分の想いで、主観でいいんだって思い始めてから、さらにドキュメンタリーが面白くなりました。ドキュメンタリーは表現行動ですから、お客さんにもそう思って観てほしい。僕は全作品を通じて主張しているつもりです」
ドキュメンタリーは監視カメラが撮るわけではありません。人の手でカメラを動かし、人が人を撮る。いろんな感性のカメラマンがいて、何を撮るかが違うだけでその時の想いがわかる。ドキュメンタリーの面白さは、カメラを通して見る主観なのだと森さんは語ります。
学生に対してメディアリテラシーを教える森さんが見る、「今」
現在、明治大学にてメディアリテラシーを教えている森さん。メディアリテラシーを扱う森さんのゼミ生の中にも、熱心な学生が森さんの背中に憧れ、ドキュメンタリー作家の門をたたく者もいます。
「30歳近くになった元ゼミ生が、いまだに『先生、先日新興宗教の宗教法人に行って映像を撮ってきました』と報告してくれて。今この話を聞いて『過激なことをしてるな』と思った人もいるかもしれません。でも、僕がそうだったように、そういう人って、セキュリティ意識があまりないんです。あるいは、逆に、今の人たちは過剰に不安や恐怖を持ってしまってしまっているのかもしれません。」
本来メディアは真実を伝える役割を担うもののはずなのに、今、不安や恐怖を伝えることだけで視聴率を上げることに注力してしまっていることが問題だと森さんは指摘していました。

不安や恐怖といえば、この出口が見えないコロナ禍。インターネットが身近になったのが1995年ごろで、インターネット文化の歴史はまだ30年足らずですが、そんな今にコロナ禍が訪れたのは「運命的ですよね。今できることを駆使して、この状況を逆に楽しまないと」と森さん。
以前のように仕事帰りに同僚とお酒を飲みに行って……といった日常ができなくなった今ですが、逆にその分できた時間を違う視点で楽しめるようになっているはずだといいます。
「ダメだったらダメで別の道、を考えたほうがずっといい」
いわゆる「レールから外れた」若者時代を送り、その後も決して平たんな道ではなかった森さんの半生。今キャリアや仕事で悩む若者たちに、森さんの経験からアドバイスするとしたら、どんな言葉を選ぶのでしょうか。
「焦らなくていいって思うんです。僕は結果的に今ドキュメンタリー映画監督とか、大学教授とかいう肩書きをもらっているけれど、29歳まではフリーターだったし、当時は本当に焦っていました。今僕が見ている学生たちも、就活の時期になると焦っているので『焦らなくていいんじゃないの』と言ったら『先生の時とは時代が違うんです』と逆に怒られることも。
でも、順風満帆に会社に入ってしっかり仕事をこなしていたけれど、何かの拍子にスリップしてしまう人はいくらでもいると思うんです。だから結果的にこの先何があるかなんてわからないし、そんなに思いつめず、ダメだったらダメで、じゃあ別な道に何があるかを考えたほうがずっと今が楽しくなりませんか」
「若いときは仕事なんて選べなかった」と森さんはいいます。それでも、選ばなかったからこそドキュメンタリーの面白さに気付き、踏み込むうちに「主観でいい」と気付けたのです。森さんの「真実と向き合う姿勢」は、こうした「焦らなくていい」考え方から生まれてくるものなのかもしれません。
(文:山口真央 編集:高山諒(ヒャクマンボルト) 写真:Ban Yutaka)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。