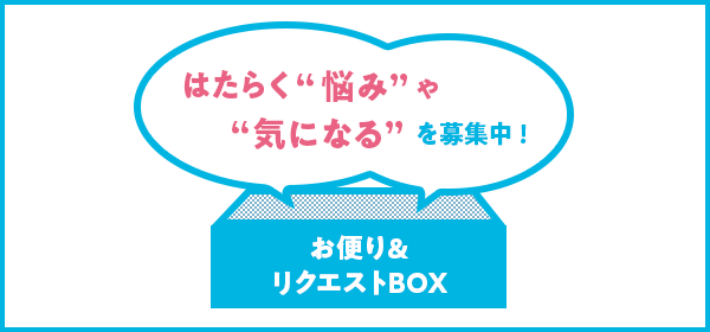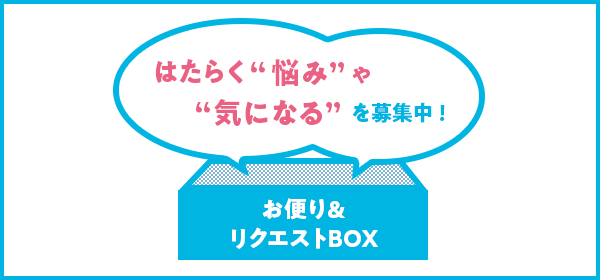- TOP
- WORK LIFE THEATER
- 大木亜希子は、なぜアイドルになり、絶望して──、作家として本当の「ジブン」を見つけたのか
大木亜希子は、なぜアイドルになり、絶望して──、作家として本当の「ジブン」を見つけたのか

捨て身になったアイドル
元アイドル、大木亜希子さん。14歳の時に芸能界デビューし、ドラマやCMに出演。AKB48グループのひとつ、「SDN48」のメンバーとして紅白歌合戦に出場したこともあります。
芸能界を離れたあとは、ニュースサイト「しらべぇ」編集部に勤務。ライター、編集者として手掛けたいくつかの記事は、大きな話題を呼びました。
そして現在は作家として、20代、30代の女性たちを中心に大きな支持を集めています。
大木さんのキャリアは、美貌と才能を兼ね備えた女性の、キラキラとした華やかな歩みに見えるかもしれません。しかし、作家に至るまでの半生を語る彼女の口からは「飛び降りたい」「偽りの自分」「セルフネグレクト」という重々しい言葉が次々と出てきました。
大木さんはこう振り返ります。
「捨て身になって、これが本当の私ですって世の中に挙手した瞬間、たくさんの人が興味を持ってくれたんです」
元アイドルは、なぜ、捨て身にならざるを得ないほどに追い詰められたのでしょうか。なにを抱え込み、なにを手放して、作家としての「今」を手にしたのでしょうか?
父親との死別
1989年、歯科医師の父と専業主婦の母の間に、4姉妹の末っ子として生まれた大木さん。千葉市の「典型的なベッドタウン」で、15歳まで過ごしました。
幼いころから本を読むのが好きで、図書館に通っていました。物心がついた時には母親が購読していた雑誌『婦人公論』をパラパラと読んでみたり、小学生のころには8歳上の長女の部屋にあった本を読むようになったそうです。
「敏感な子どもだったから友だちも少なかったし、学校の先生と折り合いが悪くなってしまうことも多くて、3カ月に一度は『もう無理!』となって、学校を休んで一日中本を読んでいる日もありました。松本人志さんの『遺書』とか、中島らもさんや田口ランディさんの本とか、まだ子どもが読むには早いと言われそうな本が好きでした(笑)」
本の虫だった大木さんが芸能界に入ったきっかけは、父親との死別。小学校4年生の時に脳梗塞で倒れた父親は、それ以来ずっと体調が芳しくなく、2005年、15歳の時に亡くなりました。そのころ、双子の姉と一緒に大手事務所からスカウトされました。後日、その事務所の社長と船橋のららぽーとで会った時に、大木さんは考えます。
「これは宝くじに当たったレベルの話だ。この事務所に入れば、姉とふたり分のお給料が得られる。大手だから、仕事ももらえるだろう」
この予想はぴたりと当たりました。地元の県立高校に通いながら女優として芸能活動を始めると、次々に仕事が舞い込みました。同年10月、土曜日21時からのゴールデンタイムに放送が始まったドラマ『野ブタ。をプロデュース』にも出演しています。
この番組で、ある人気俳優と腕を組むシーンが放送された翌日、大木さんの環境は大きく変わりました。県立高校の、いわゆる普通の高校生たちのなかで飛び抜けて目立ってしまったことで、同級生たちのなかで羨ましさや妬みなどが一気に噴出したのでしょう。
「それまで一緒に行動をしていた子を含めて、ほとんどのクラスメイトから無視されるようになってしまったんです」
そのまま同じ高校に通っていると今後の活動に差し支えるということで、高校2年生の時、都内の芸能コースがある学校に転校。親元を離れ、双子の姉とふたり暮らしをしながら、芸能界での成功を目指す日々が本格的に始動しました。
「経験値がないまま社長になっちゃった」
クラスメイトは、学校を離れた瞬間に皆がライバル。放課後は毎日何かしらのレッスンを受けるか、オーディションがあり、友人と遊ぶような時間はありません。毎日体重測定があり、0.1キロでも増えたら注意を受けます。息つく暇のない生活を送るも、芸能活動に手ごたえを得ることもないまま、大木さんはただ必死に食らいついていました。
「オーディションで決まる仕事もありましたが、大半は事務所の力で取ってきた仕事でした。経験値がないまま社長になっちゃったみたいな感じです。実力がないから、空っぽの中身を埋める作業をやらなきゃいけないんだけど、私はそのやり方がわからなかったので、まずは自分を知ろうと思って哲学書や『自分とはなにか』的な自分探しの本を読み漁っていました。あの時は、本だけが頼りでしたね」
芸能界の競争は残酷です。売れっ子になってあっという間に羽ばたいていく人と、いつまでも低空飛行を続ける人が露骨に分かれます。大木さんは、後者でした。19歳のころには明らかに仕事が減り始め、その時にはもう、自己肯定感を喪失し、自尊心が徹底的に傷ついて、疲れ果てていました。ある日のこと。山手線の新宿駅のホームで、衝動的にこう思ったそうです。
「……死にたい。飛び降りようかな」
いやいや、それはダメだと思いとどまる理性は残っていましたが、この時、「芸能活動はもうやめよう」と決めました。
紅白歌合戦に出場した日
そのタイミングで、「SDN48という20歳以上のグループがあるから、オーディションを受けてみない?」と知り合いの芸能関係者から声をかけられました。主に土曜夜に公演を行うことからSaturDayNightの頭文字をとって命名されたSDN48は、当時は既婚者もいるAKB48グループの中で異色の存在でした。
大木さんは「もうちょっとだけ頑張ってみよう」とオーディションを受け、審査合格後、加入することになったのですが、アイドルの生活は想像以上に過酷なものだったと言います。
時には1日10時間以上も歌とダンスのレッスンがありましたが、大木さんは歌とダンスが苦手で習得するのが遅く、ステージに立つのがほかのメンバーよりも半年遅れました。女優時代は「キャピキャピするな。その場にいるだけで周りが勝手に動くようなカリスマ性のある人間になれ」と教育を受けたのに、アイドルは常に笑顔を浮かべて親しみやすく振る舞うことを求められました。女優とアイドルのギャップを埋められず、握手会で並んでくれるファンも多くありませんでした。
「プライドだけはあるから、アイドルとしての自分をまったく消化できなかったんです。本当の自分と、アイドルとしてプロデュースされている自分のずれがしんどかったですね」
2011年の大みそか、大木さんはAKB48グループの一員として、紅白歌合戦に出場しました。しかし、喜びはありませんでした。
この日、与えられた役割は「頑張ろう!日本」という人文字の「!」の下の点の部分。画面に映ったのはほんの一瞬で、出演が終わったらすぐに帰宅が許され、実家で年越しそばを食べながら番組の続きを観ていたそうです。そのとき、「私、なにやってんだろ」と疑問が募ったと言います。
トイレ掃除をしている時に出会ったファン
翌年3月、SDN48が解散。大木さんは、姉とともにアルバイトで生活費を稼ぎながら地下アイドルとして芸能活動を続けることにしました。そこはまた、茨の道でした。
女優、アイドルとして世間に顔を知られているので、着ぐるみのなかに入りスーパーの買い物客にお菓子を配るバイトやビジネスホテルでのベッドメイキング、トイレ掃除のバイトなど顔を晒さなくて済む仕事をする日々。SDN48を辞めてから日に日に熱心なファンが離れていき、2年が経ったころには片手で数えられるほどになってしまいました。
アイドルとしてライブに立った日の翌日に、ホテルのトイレ掃除のアルバイトをしていた時のこと。SDN48時代に応援してくれていたファンが、バシッとスーツを着て歩いてきました。その人のことをハッキリ覚えていた大木さんは、ハッとしました。しかしそのファンは、三角巾をかぶり、白い制服でトイレ掃除をしている大木さんに気付かず、通り過ぎていきました。この時の衝撃は、今も忘れられないそうです。
「私、このまま何者になっていくんだろう」という言葉が頭のなかでループする日々のなかで、ある日、ニュースサイト「しらべぇ」編集部にコラムを書かせてほしいとメールを送りました。
「24歳にもなって、しかも芸能人としてそんなに売れているわけでもないのに、名刺の渡し方ひとつ知らず、新幹線のチケットもろくに買えない。社会人として常識が一切身に付いておらず、私、マジで終わってんなと思ったんですよね。ちょうどその時、漫画喫茶でネットサーフィンしていて、しらべぇ編集部の記者募集を見つけて、すぐにメールで応募しました。そのころ、自分には何もないと思っていたんですけど、以前から、ファンの方がSNSの文が章面白いと言ってくれていたから、それを信じるしかなかったんです」
芸能界で知りあった「まだそれほど有名になっていないけど面白い芸人さんやタレントさん」を取材して紹介したいと自己アピールを記したところ、編集部からは採用の返事が来ました。そのメールを見て小躍りした大木さんは、地下アイドルを続けながら、ライターとして、自分のすべてを注ぐ勢いでコラムを書き始めました。
普通の女の子として生きてみたかった
その熱意が届いたのかもしれません。メールを送ってから半年後の2014年末、「しらべぇ」編集部の忘年会に呼ばれました。その時、編集長から「営業職に興味があったら、うちでいつでも雇ってあげるよ」と誘われました。飲み会の場でのジョークだったのかもしれませんが、大木さんはその言葉を聞いて、アイドルを辞めることを決めました。
「その時の私は、固定給で社会保障が手厚い仕事に憧れていたから、編集長に本当に雇ってくださいと言いました。今思えば、会社員になりたいというよりは、普通の女の子として生きてみたかったんですよね。15歳から25歳まで、ずっと普通じゃなかったから」
2015年6月、「しらべぇ」を運営する企業の会社員になり、ライター、編集者として活動を開始。ワード、エクセル、パワーポイントの使い方、ビジネスメールの打ち方などはイチから教わりました。社会人としての基礎を叩き込まれながら、1日に数本の記事を書くようになり、記事広告を販売する営業も担当しました。
目まぐるしい日々のなかで、大木さんはライターとしての自信を深めていきます。入社してすぐに配信された「おっさんレンタル」を特集した記事は、SNS上で広くシェアされて大ヒット。それ以降も、何度もSNS上で話題になるような記事を手掛けました。その過程で、傷だらけだった自己肯定感や自尊心が少しずつ回復していきました。
「自分の記事がライターとして評価されることで、これまで女優やアイドルとして日の目を見なかったという怨念がどんどん浄化されていきました。父の死があって芸能界に入ったけれど、私、別に表に出たかったわけじゃないんだと気付いたんです。自分で取材のアポを取って、自前のカメラで写真を撮って、記事を書く。そのすべてが楽しくもあり、社会的意義も感じられて、自分の存在をようやく認められた気がしましたね」
人生が完全に停止した日
認められると、欲が出てきます。芸能界では成功できなかったけど、社会人として勝ち組になれるかもしれません。
営業先で、「気が利く女の子」としての振る舞うと喜ばれました。プライベートでも、飲み会に行けば元芸能人として扱われました。求められれば、相手が望んだ通りに感じの良い子を演じました。そうして広告を取ることで上司に褒められ、営業も獲得し、喜びを感じることが出来ました。
しかし、それは決して「普通の女の子」ではありません。過去の栄光を振りかざし、「キラキラとした女性」をアピールしているうちに、なりたかったはずの自分からどんどん遠ざかっていきました。気づけば、会社員になってから体重が20キロも増えていました。それは、勝ち組になろうとが自分を演じていたストレスの表れだったのかもしれません。
そして3年目、28歳の時、胸のうちで膨らみ続けていた矛盾がついに弾けました。仕事に向かう地下鉄のホームで、スイッチが切れたように足が前に進まなくなってしまったのです。上司に「体調不良」と連絡し、友人から勧められた心療内科に向かいました。
その時は「たいしたことない」と思っていたので、医師に対して「これぐらい大丈夫です」などと話していたら、「大木さん、落ち着いてください、まずその早口をなおしましょう」と言われました。その言葉で頭に血が上り、「私は大丈夫なのに!」と憤慨しましたが、そのこと自体が心身に良くないことが起きていることの証でした。
「仕事は楽しかったけど、女優やアイドルとしてうまくいかなかった時となんら変わらず、「キラキラした偽りの自分」を演じて、無理をしていたんです。15歳から28歳までエンジンのオイル交換なしで走り続けた結果、一旦、人生が完全に停止しちゃいました」
友人に弱音を吐いて気づいたこと
朝、起き上がることもできなくなり、やむなく会社を退職。毎日、都心にある心療内科に通うことだけが日課になりました。医師から「人生を棚卸ししましょう」と言われ、芸能界に入った時のことから話をしていきました。
病院を出るといつも、おしゃれなマダムやビジネスパーソンが都会の街を闊歩する姿を目にします。そのたびに、「私、終わっちゃったみたい。ヤバい……」という想いだけが募っていきました。
このどん底の時期に、高校の芸能コース時代をともに過ごした友人たちと顔を合わせ、「なんでこんなに大変な状況になるまで言ってくれなかったの?」と嘆かれました。それから友人たちはあれこれと世話を焼いてくれました。インタビュー中、友人たちとのやり取りを振り返った大木さんは、目を赤くしました。
「この時、人に弱音を吐いてもいいんだなと思えたんですよね。それまでは、弱音を吐いちゃいけないって思い込んでいたんです。芸能の仕事をしていると一般の仕事に就くお友達にはまず言えないし、同業はライバルでしょう。会社員になったら、周りからキラキラして見られたかった。だから、知らぬ間に自分から孤独になっていったんです」
一時期は、毎日すっぴんでジャージ姿、外に出るのも億劫で、家でゴロゴロしている状態でしたが、友人たちの献身的な心遣いによって、少しずつ前向きになっていきました。
朝はゆっくりと起きて、昼間は図書館に行き、気が向いたら、友人が紹介してくれた段ボールの梱包や解体をするアルバイトに向かう。そこには友人がいて、一緒にはたらきながら、笑いあう。キラキラする必要もなく、向上心を持て、勝ち組を目指せと煽る人もいません。なにげない淡々とした時間の流れが、乾ききった心を潤していきました。
56歳の「おっさん」との共同生活
しかし同じ時期、貯金は失われていきました。そうして残高が3万円になった2018年5月、8歳上の姉がかつてルームシェアをしていた一般企業に勤める男性、当時56歳の通称「ササポン」と同居することになりました。見ず知らずの「おっさん」と一緒に住む抵抗感や恥ずかしさを飲み込まざるを得ないほど、金銭的な危機が迫っていたのです。
都心部の閑静な住宅街にある3階建ての一軒家で、ササポンとの共同生活は始まりました。互いに負担に感じない距離を保ち、なにも押し付けてこず、でもさりげなく気にかけてくれるササポンとのシンプルな日々の中で、凝り固まった大木さんの価値観が緩やかに溶けていきました。大木さんは、「彼に支えられたとか救われたんじゃなくて、彼が私自身の鏡になっていたんだと思う」と語ります。
「私はずっと、30歳までに年収がいくらなきゃいけない、ハイスペ男子と結婚しなきゃ生きていけない、家賃これぐらいのところに住まなきゃいけないと自分でがんじがらめになっていました。でも彼はまったくそういう概念がない。私はこんなにこんなに生きづらい想いをしてるのに、それとまったく無縁の彼の価値観に触れた時に、がちょーんって衝撃を受けたんです(笑)」
なにかを達成しなきゃいけないという呪縛から自由になると、心が軽くなります。会社を辞めてからしばらくは、フリーライターになったと言っても開店休業状態でしたが、仕事を獲得するため営業をする元気が湧いてきました。時には下心丸出しの編集者に遭遇したり、編集者に打ち合わせの予定をすっぽかされたり屈辱的な経験をしたこともありましたが、めげずに売り込みを続けました。
捨て身になった瞬間に起きたミラクル
それでもなかなかうまくいかず、将来に迷っていた2018年の12月、一本の記事を書きました。それは、苦難のアイドル時代からササポンとの生活に至る自分の半生を記したコラムで、タイトルは「人生に詰んだ元アイドルは、赤の他人のおっさんと住む選択をした」。
新しく出来たばかりのメディアに書いた記事で、「そんな反響はないだろうな」と思っていたそうですが、公開から間もなくしてスマホの通知がとんでもないことになりました。Twitterではリツイートの数が数千に達し、トレンド入り。著名人が何人もコメントを寄せていました。ダイレクトメッセージと仕事用のメールには、10社以上から出版依頼と取材依頼が届きました。
アルバイト先で、想像を絶する反響に呆然とした大木さんは、帰宅した後、ササポンに「ネットで有名なおじさんになってます」と告げました。コーヒーを飲んでいたササポンに「あ、そうなんだ」と軽く流されて、その反応にまた「がちょーん」となりました。
実はまったく同じ時期に、薄いつながりをたどり、当たって砕けろで出版社に提案した書籍企画が採用されました。AKBグループを卒業した元アイドルの女性のセカンドキャリアを追った『アイドル、やめました。 AKB48のセカンドキャリア』の企画です。
「この2つの出来事は、2018年の10月から12月の2カ月間に起きました。自分が捨て身になった瞬間に起きたミラクルでした」
このミラクルが強烈な追い風になり、大木さんの人生を変えました。星の数ほどいるライターの一人としてではなく、「大木亜希子さんの原稿が欲しい」という依頼が一気に増えたのです。
それでも会社員時代のように舞い上がらなかったのは、元アイドルとして愛想を振りまくことでも、キラキラ女子を演じることでもなく、等身大の自分を描いた原稿を求められるようになったからではないでしょうか。自分も、原稿も、飾ることをやめたら、依頼もファンも増えていきました。
最近は、『小説現代』(講談社)をはじめ多くの大手文芸誌で作家として小説も発表している大木さん。会社員時代は「勝ち組になるため」に仕事をしていましたが、今は読者のことを想って原稿を書いているそうです。
「昔の自分だったら、ネガティブなことを言われるとすぐに落ち込むぐらいメンタルも弱かったし、こんなことを書いたらお嫁に行けないんじゃないかとか、色物に見られたくないとか、他人の目を気にしていたんですけど、今はどう捉えていただいても構いません。むしろ、男性に依存することも辞め、働いて自分の足で立つことで自信が持てるようになりました。私のことはどうでもいい。私が自分の人生を書くことで救われる人がいるなら、その人たちにためにも役立つ物語を書かせていただきたいと思っています」
(文:川内イオ 写真:小池大介)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。
あなたにおすすめの記事
同じ特集の記事
近著に『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(2019)、『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(2020)。
人気記事
近著に『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(2019)、『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(2020)。