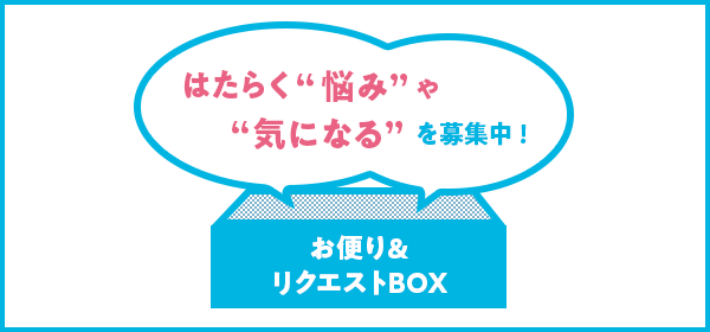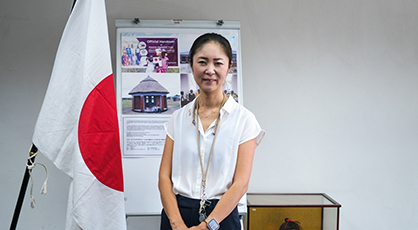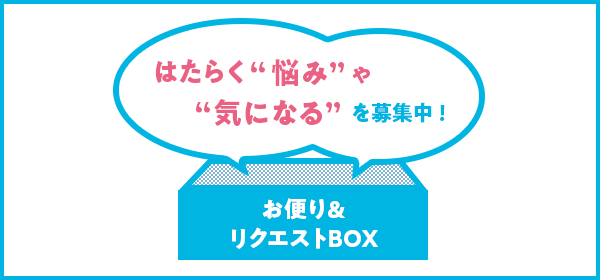- TOP
- WORK LIFE THEATER
- 侍ママ、NYへ。米国で殺陣道場を開く香純さんは「伝わらない」にどう向き合ったのか
侍ママ、NYへ。米国で殺陣道場を開く香純さんは「伝わらない」にどう向き合ったのか

アメリカで唯一の殺陣道場を開く女性
時代劇の見せ場のひとつ、「殺陣(たて)」。素手、もしくは刀などの武器を持って格闘する一連の演技を指す言葉です。明治時代に歌舞伎から派生したもので、日本独自の技術、精神は映画やドラマなどを通じて現代まで脈々と受け継がれてきました。
この殺陣を、アメリカで広めようと一人奮闘している女性がいます。アメリカで唯一の殺陣の道場、TATE Hatoryu NY(殺陣波濤流NY)を開く殺陣師、香純 恭(かすみ きょう)さんです。
香純さんは、もともと日本でモデル、タレントとして活動していました。そこからなぜ殺陣に惹かれ、アメリカで道場を開くことになったのか。まずは、そこから振り返りましょう。
『チャーリーズ・エンジェル』に憧れて

子どものころから体を動かすのが好きだった香純さんは、体育教師を目指して東京女子体育大学に進学。卒業後は、中学校の非常勤職員として勤務していましたが、「教員は聖職」という理想に縛られ、次第にその重圧に苦しむように。プレッシャーから逃れるようにして、教職から離れました。
「本当に自分がやりたかったことってなんだろう」
思い出したのが子どものころの夢でした。小学生のときに大好きだったのは、女性たちが目の覚めるようなアクションを見せるアメリカのドラマ『チャーリーズ・エンジェル』の再放送。テレビで観た翌日には、近所の男の子たちを悪役に見立てて、エンジェルになり切っていました。
「私が本当にやりたかったこと、それはアクション女優だ」と気付くまでに、そう時間はかかりませんでした。
芸能界についてなんの知識もなかったため、何かのきっかけになればと、友人に勧められた「第2回モーターボートクイーンコンテスト」に応募。
そこで準グランプリを受賞したことで、大手芸能事務所に所属することになります。
故 高瀬将嗣さんとの出会い
それからは、CMやバラエティー番組に出るなど、タレントとして活動するように。
華やかな芸能界の仕事は楽しく、充実していましたが、アクションの世界からは遠のくばかり、自問自答の日々が続きました。
「やっぱり、アクションがやりたい!」と、舞台に立っていた友人に相談したところ、「厳しいけどすごいところあるよ」と紹介されたのが、芸道殺陣波濤流高瀬道場(げいどうたてはとうりゅうたかせどうじょう)。

高瀬道場は府中に道場を構えるアクション俳優や殺陣師たちが所属する芸能事務所。友人と初めて道場を訪ねたとき、その雰囲気に驚いたそうです。
「最初はちょっと見学させてもらおうという軽い気持ちで、派手な格好で道場に行ってしまったんですが、完全に場違いでしたね。
稽古が始まったらすごい緊張感で、空気も重い。なんなんだこの道場と思いながら、声も出せずにお稽古が終わるまでじっと座っていました」
稽古が終わった後、強面の風貌で並々ならぬ迫力の主宰者として知られる、故 高瀬将嗣さんから「で、いつから来るんだ、明日か?」と聞かれた香純さんは、「は、はい!」と答えるのが精一杯。
実際には、再訪したのは翌日ではなく、数日後だったそうですが、そこで「雷が落ちたような衝撃」を受けます。
「初日なので基本を教わったんですが、最後に5手、6手ぐらいの簡単な立ち回りをさせてくれたんです。
そのときに、向かってくる相手をバサバサと切る所作を初めて体験したんですけど、物語の中に入れたような瞬間があって。
それがいままで観てきたアクションの世界と重なって、うわ、楽しい!って身震いするような衝撃を受けたのを今でも覚えています」
「電車賃がある限り通う、なければ泊まる」

この日以来、「1時間でも多く道場にいたい」と思うようになった香純さんは、道場に通いつめ、時には泊まり込んで稽古するように。1年が経つころには、所属していた芸能事務所を辞めて、高瀬道場への弟子入りが認められました。
弟子入りから数年後に結婚し、出産。師匠や道場の仲間たちは、子連れで稽古に来ることを歓迎し、香純さんが道場の一員として舞台に立ったり、仕事をしているときは、率先して子どもの世話をしてくました。
恵まれた環境に感謝し、よりいっそう、稽古に打ち込む日々。それもあって、夫が「アメリカに留学したい」と相談してきたときは本当につらかったと言います。
「アメリカに行くには、自分の生きがいであり中心軸である道場や殺陣を捨てなくちゃいけないと思っていたので、その選択をするのがつらくて。本当に泣きまくりました」
当時、母親の体調が悪かったこともあり、自分と子どもは日本に残ろうと考えたこともありました。
しかし、父親から「俺の女房は俺が面倒をみるからほっとけ。お前の旦那は、お前が面倒を見ろ。絶対ついていかなきゃだめだ」と言われたのがきっかけで、渡米を決意。
2008年、0歳、2歳、5歳の子どもを連れて、ニューヨークへ。

予想もしなかったクレーム
子どもが幼かったこともあり、初めての海外生活はてんやわんや。子育てをしながら、英語を覚え、アメリカの文化や習慣に慣れていくのは、簡単なことではありませんでした。
毎日が怒涛の勢いで過ぎていく中で、それでも時間を見つけて自宅で殺陣の稽古をし、興味を持つ人がいれば、慣れない英語で説明しました。
そんなある日。子どもが通う幼稚園から「異文化交流会で殺陣の演舞を見せてほしい」というオファーを受けます。香純さんは、アメリカで殺陣を披露できるなんてありがたい機会だと快諾しました。
しかし前日の夜、幼稚園から突然「キャンセルさせてほしい」と電話がかかってきたのです。
話を聞くと、園児の保護者から「小さい子どもに殺人の方法を教えるなんてとんでもない」とクレームが入ったことがわかりました。
アメリカでは殺陣についてまったく知られておらず、マーシャルアーツ(武道)ではなくて、日本の伝統的なパフォーミングアーツ(芸道)であることが理解されていなかったのです。そのとき、香純さんは「そうか、アメリカで殺陣を広めるなら、ここからスタートしなくちゃいけないんだ」と痛感したと言います。

「絶対に殺陣を習いたい」で目が覚めた
夫の留学は2年で終わり、2010年に帰国。また子育てしながら道場に通い、仕事をするという日々に戻りました。そして2年後、家族の都合で再びアメリカに渡ることに。拠点は同じニューヨーク。最初の2年間で必死に築いたコミュニティが、カムバックを歓迎してくれました。

それから1年ほど経った、ある日のこと。知り合いツテに面識のない人から、「子どもに殺陣を教えてほしい」という連絡がありました。周囲の友人、知人は香純さんが殺陣をやっていると知っているので、どこからか噂を聞き付けたようです。
香純さんは「いいですよ」と返信。後日、父と息子が自宅に訪ねてきました。その13歳の少年に簡単な稽古をつけると、その日の夜、父親からメールが届きました。
「息子が、好きというレベルじゃなくて大好きになったから、絶対に殺陣を習いたいと言っている」
この言葉を目にした瞬間、目が覚めました。
「2回目に来たときは、ここで道場ができたらいいなと思っていました。でも、殺陣って専門用語ばかりなので、どう英語に直していいか見当もつかない。
まだ子どもも小さかったし、踏ん切りがつかなかったんです。
でも、メールを読んだときに、なにを怖がってたんだ。こんな子がひとりでもいるなら、やらなきゃ駄目でしょ、と思えたんです」
腹をくくってからの行動はスピーディーでした。夫が出張中に、自宅の地下室を道場にリニューアル。生徒を募集するために、まずは殺陣とはなにかを知ってもらおうと、あらゆる知り合いに声をかけて演武会を開きました。
すると、香純さんの存在と道場を開きたいという想いが口コミで広がり、学びたいという人が何人も連絡してくるようになりました。その後も、知り合いのツテをたどっていろいろな場所で演舞をしているうちに、門下生が増えていきます。
異文化の壁をどう乗り越える?

ただし、それで浮かれている暇はありません。すぐに、「自分が今まで培った技術や教え方、そのすべてが、なにひとつ通用しない」ということに気づいたのです。
たとえば、一列に並んでほしいと言っても、誰も整列しません。日本人なら小学校で習うことですが、そもそもアメリカでは体育の授業でも一列に並ぶことがないのです。
稽古を始める前に黙想をしようとしても、彼らはどういうことかが理解できません。目を閉じてじっとする文化も習慣もないので、2、3秒で目を開けて動き出してしまうのです。
稽古が終わった後、道場を掃除するのは日本では当たり前のことでしたが、「なぜうちの子どもに掃除をさせるのか」と保護者から苦情が来たこともありました。
「最初のころは、育った環境や文化が異なると、こんなに違うのかって毎回驚きでした。でも、それを理解しながらやらないと、この国で道場はできないと感じましたね。
だから、自分のやり方を押し付けず、相手に合わせながら、いつも『BECAUSE』をつけて、私が何をしたいのか、どうしてそういうふうにしてもらいたいのかを少しずつ、根気よく伝えました」
技術指導でも、苦労は絶えません。たとえば、「刀を受けて、払う」という基本の動作ひとつとっても、該当する英語を考えなければいけません。
これはいくつかの候補を考えた末に「ブロック&スウィープ」で落ち着きました。同じように、足運びの動作「歩み足」はウォークステップ、「継ぎ足」はハーフステップ。
うまく英語で表現しないと生徒がちゃんと意味を理解して動けないので、生徒と相談しながら、一つひとつの動作に名前を付けていきました。
教え子たちの変化

香純さんはただただ必死でしたが、そのまっすぐな指導が評判を呼び、次第にプロの俳優やパフォーマーも学びにくるように。
そこで、2016年にはマンハッタンクラスも開校。自宅の地下の道場と2カ所を掛け持ちするまでになりました。このころには、生徒も明らかに変わり始めます。
「殺陣はパフォーミングアーツなので、相手のためにどう動いたらいいのかを常に考えることが大切なんです。
あるとき、高校生のクラスでひとつの動作を何秒でできるのか測ったんですが、最初は、お前が遅い、お前が悪いとケンカになりました。
でも、途中で自分ひとりだけ早く演じても意味がないとわかると、相談が始まったんです。
それから、誰が一番じゃなくて、チームで何秒縮められるかに目標がシフトされました。その姿を見て、確かな変化を感じましたね」
香純さんの教え子の中で、最も顕著に変化したのは、この高校生クラスの子どもたちでした。

外部業者の仕事という感覚だった掃除も、今では香純さんがモップをもって掃除をしようとすると、僕がやるよ、と代わってくれます。それだけでなく「なにかヘルプできることはない?」と聞いてくれる。そんな気遣いもしてくれるようになりました。
香純さんは「私は、アメリカで殺陣を教えることで教え子たちに成長させてもらいました。人生にとってものすごく大事な機会だったと思いますし、彼らもそう思ってくれています」と語ります。
殺陣をもっと広めるために
殺陣のクラスが軌道に乗り始めた2017年には、「NYを舞台にした、女性が主役の殺陣の映画を作りたい」と思い立ち、19世紀に最初にアメリカに移住してきた侍をテーマに映画の制作にも挑戦。

あちこちでプレゼンし、少しずつお金を集めて作った初プロデュース作品『First Samurai in New York』は、ロサンゼルスで開催された「Artemis Women in Action Film Festival」(2018)で、最優秀ファイト・ウエポン賞を受賞しました。

映画の制作で大きな手ごたえを得た香純さんは、本格的に現地の映画やドラマで殺陣の指導を始めようと考えています。
現在は、オンラインクラス含め、ひと月に50~60クラス開きながら、コロナが落ち着いた後の計画を練る毎日。
オフブロードウェイに殺陣をとり入れた舞台「忠臣蔵」の実現に向けた準備も進めているそうです。

文化や習慣の違いを認め、理解しようと努めることで、アメリカで殺陣師としての人生を切り拓いてきた香純さん。その原動力は、「信じてやまないパッションと、信じてくれる生徒達です」とほほ笑みました。
「今の目標は、この殺陣という日本の伝統が詰まった素晴らしい動きの数々を、海外の映画や舞台に使ってもらうこと。いずれ、殺陣という言葉が寿司や折り紙のように、海外で普通に使われる単語になってほしいですね」

(取材・文:川内イオ 写真提供:香純恭、株式会社ガイズエンタティメント)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。
あなたにおすすめの記事
同じ特集の記事
近著に『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(2019)、『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(2020)。
人気記事
近著に『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(2019)、『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(2020)。