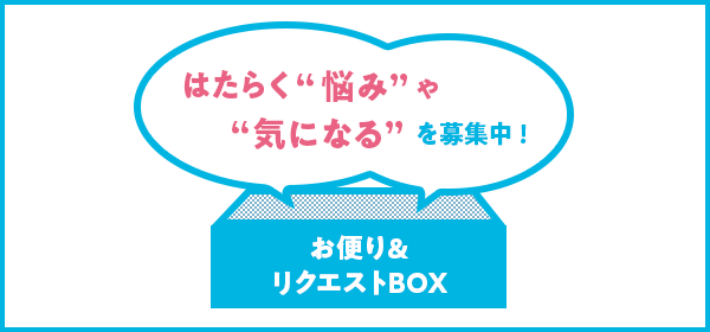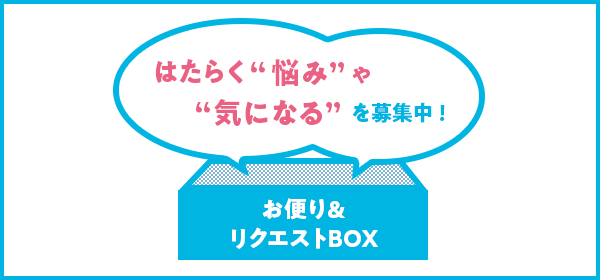「ケアビューティスト」のMiyabiさんが語る、“介護美容”の醍醐味

「多分私、お年寄りが大好きなんだと思います。おばあちゃん子だったので、おばあちゃんが生きていたらやってあげたかったなぁ……と思うことがたくさんあって」
ケアビューティストのMiyabiさんは目を細めます。
高齢者施設に出張してヘアカットなどをする“介護美容”という言葉が知られるようになって久しいですが、「ケアビューティスト」は、メイクやネイル・リラクゼーションを専門に高齢者の方たちを美しくする、新しい職業です。
「もう一回お嫁に行けるわね!」
「お洒落をしないなんて、裸で歩いているのと一緒よ」
ケアビューティーを受けた女性たちは口々にこう言います。Miyabiさんが介護に携わるようになったのは、約3年前。それまでは、異色の職業に就いていたといいます。現在までに至る軌跡を伺いました。
幼いころから憧れた、華やかな表舞台
岐阜県の山あいで生まれ育ったMiyabiさんは、アイドルや歌、ダンスが好きな、ごく普通の女の子でした。
生まれたころから父方の祖母と同居しており、祖母は裁縫が大の得意でした。夏には浴衣を縫ってくれ、Miyabiさんは一度も市販の浴衣を買ったことがありません。Miyabiさんは祖母のことが大好きで、中学生になるまでほぼ毎晩、祖母と同じ布団で寝ていました。
中学生の時、父の転勤で名古屋へ。祖母の影響で洋服づくりに興味のあったMiyabiさんは、家政科のある高校へ進みました。しかし、洋裁のほかにも調理や保育を学ばなければならず「やりたいことはこれじゃない!」と中退し、コンビニでアルバイトをしながら、独学で洋服づくりに励みました。
20歳になったある日、道端でモデル事務所からスカウトを受けます。Miyabiさんの中でモデルのイメージは、洋服を美しく魅せる仕事。両親は娘のやりたいことを反対せず、幼いころから表舞台に憧れていたため、そのままモデルの世界へ飛び込みました。
ところが、なかなか事務所では思っていたような案件を担当できず、25歳ごろでフリーのモデルへ転身。洋服ブランドのカタログに出たり、フィッティングモデルをしたり……それはMiyabiさんがやりたかったことで、ただただ楽しく、やりがいを感じていました。
そうしたモデルの仕事は、生活のために掛け持ちしていた、六本木や銀座にあるクラブのホステスのアルバイト先で紹介されることがほとんどでした。
Miyabiさんいわく、そこは「女同士の戦場」。お客さんからの指名を争っていじめが起きることも日常的でしたが、Miyabiさんは自身を「ポジティブお化け」だといい、「その人たちを味方につけるまでのプロセスに、逆に燃えちゃうんです(笑)」と話してくれました。
30代になるとお客さんからの紹介でタレントマネージャーの仕事も始め、一時は3足のわらじを履いて生活していました。
皆、温もりを求めていた
タレントマネージャーはスケジュールが過酷で、Miyabiさんは「長く楽しく続けられる仕事」を探していました。2019年のある日、Instagramをなんとなく眺めていると、ある広告が目に入りました。それは、介護美容研究所という、ケアビューティストを育てるスクールのものでした。
Miyabiさんはそれまで、介護に興味があるどころか、「汚そう」「大変そう」というネガティブな印象を抱いていました。ところが気になって読み進めていくと、ケアビューティストはあくまでも高齢者の方たちを美しくする仕事で、入浴や排泄介助はないようでした。
その時Miyabiさんの中で、かつて仕事で目にした、韓流スターのイベントに着飾ってお洒落をして来ているおばあちゃんたちの、キラキラした姿がふと思い浮かんだのです。
「一生お洒落を楽しむお手伝いができるなんて、素敵だな」
Miyabiさんは純粋にそう思い、1年間の「ケアビューティーコース」を受けることにしました。

「でも、いざ勉強し始めて、ケアビューティストになった時のことを考えたら、介護士の資格を持っていたほうが依頼する側も安心だよな、と思ったんです。コロナ禍で、ケアビューティストの採用基準も、看護師や介護士の資格が必須だったりと厳しくなっていました。それで、在学中に改めて、介護士の資格を取ることにしたんです」
Miyabiさんは、スクールに通いながら介護士の資格を取る方法を探しました。すると、資格取得後に介護職に就くことを条件に、学費や資格取得費が東京都から全額支給されるスクールを見つけたのです。
そこで取れる資格は、「介護職員初任者研修」。ホームヘルパー2級と同等と言われていて、介護士を目指す人がまず取得する資格でもあります。Miyabiさんは3カ月かけて資格を取り、まずは週1回の「訪問介護」のパートをすることにしました。
訪問介護は、高齢者の自宅へ行き、基本1対1で、家事や入浴・排泄や着替えの介助します。
それまで、側から見ると華やかな職に就いてきたMiyabiさんにとって、初めての訪問介護現場は衝撃的でした。お年寄りは目も合わせてくれない。ちょっと肩をポンポンとしたら叩かれる。慣れない排泄介助……。
ただ、それ以上にMiyabiさんがショックを受けたのは、見習いとして付いて回っていた先輩ヘルパーさんたちの、お年寄りへの対応でした。決められた作業を機械的に行い、さっと帰る。
それはあまりにも淡々としていて、「なんて冷たいんだろう……」とMiyabiさんは落ち込みました。訪問する先々のおばあさんの姿に、大好きだった自分の祖母が重なって見えたのです。
一人で現場に入るようになったMiyabiさんは、あることを必ずするようにしました。それは——
「訪問介護でお伺いする方は、ほとんどがお一人暮らしなんですね。だから皆さん、淋しさと、“一人ぼっちにされていることに対する怒り”がすごいんです。たとえば、ある女性の方は末期がんを患っていたのですが、日々家に来るのはヘルパーと、トイレのドアの開閉が一定時間ないと飛んでくるセコムだけ、という状態で。
私は女性なので、同性である女性の方を担当することが多かったのですが、息子さん、娘さんに対して、『育ててあげたのに』とか、『こんなに放ったらかしにして』とか……とにかく皆さん、孤独感から『温もり』を求めていらっしゃいました。なので私は、ハグしました。ぎゅって抱きしめると、人間って愛情ホルモンが出て、心が落ち着くんです。子どもでもお年寄りでも、それは変わらないなって」
ハグだけではなく、Miyabiさんは、業務に支障をきたさないよう、空いた時間でマッサージや爪のケアをしてあげました。入浴や排泄介助は「大きな赤ちゃん」だと思うようにすると、不思議と抵抗がなくなりました。

あるおばあさんは、Miyabiさんが担当して2週間で亡くなりましたが、最後まで「本当にいい人に巡り合ったわ」と呟き、
ある90代のおじいさんは、Miyabiさんと会話する時間がほしいからと、寝たきりだった体を起こし、Miyabiさんが本来やるはずの掃除・洗濯・料理をやろうとしました。
最初はMiyabiさんと目も合わせず、Miyabiさんが触れると叩くことを繰り返していたおばあさんも、亡くなる寸前に、「あなたのつくったチャーハンが食べたい」と言いました。Miyabiさんが冷蔵庫にある材料でつくると、病気でほとんど食事が喉を通らないにもかかわらず、「美味しい。ありがとう」と笑顔になったといいます。
ハグやマッサージは、介護のマニュアルにはありません。むしろ介護の現場では、必要以上に高齢者に触ることは推奨されていませんが、Miyabiさんは、できるかぎり温かみのある介護を心掛けました。
同調すること、味方になること
Miyabiさんは、「ホステスの仕事でいろいろな方とお話しした経験が、今も役立っているんです」と話します。
ホステスは経営者をはじめ、多彩な職種のビジネスパーソンを相手にするケースも多く、女性と接する機会もあります。女性の職場であることはもちろん、利用客の奥さんから、怒鳴り口調で電話がかかってくることもあるのだといいます。
Miyabiさんはそんな時、必ず共感の言葉を掛け、彼女たちの味方をしました。
すると次第に、Miyabiさんが相談相手のようになっていくのです。ある奥さんは、「あなたのところにだけは行かせるようにするわ」と言うまで、Miyabiさんに心を開いていたそうです。
「負けず嫌いなので、諦めたくないんですよね。怒っている女性に対する接し方も、すごく研究しました。何よりも大切なのは、同調すること。ご高齢者の場合も同じで、怒りや淋しさに対して『そうだよね……』と声を掛けて差し上げると、スムーズに心を開いてくださるんです」
訪問介護のパートを始めて2カ月後。Miyabiさんは「介護の仕事をもっと知りたい」と思うようになり、シフトを週4回に増やしました。この時、Miyabiさんは気付いていました。先輩ヘルパーさんたちが淡々としていた理由。それは、感情を入れすぎると後が辛くなるからなのだ、と。
それでも2年間、Miyabiさんが訪問介護のスタイルを変えることはありませんでした。
2021年6月、いよいよケアビューティストとして独立したMiyabiさん。通っていたスクールの紹介で、まずは2件のホスピスを訪れることになりました。ホスピスとは、終末期の患者さんが最期を穏やかに過ごすための施設です。
初めて担当したのは、自分と同じくらいの年齢の、若い女性でした。
「最初はおばあちゃんと若い女性が手をつないでロビーを歩いていたので、その女性の方はお見舞いに来ているのだと思ったのですが、『また来るからね』と帰っていったのはおばあちゃんのほうで。その女性の方は、ネイルを『あ、やりたい!』と喜んで受けてくださいましたが、次の月に伺うと、お部屋にはもう別な方が入られていて……。ホスピスは、入れ替わりもすごく激しいんです」
当時、ケアビューティストとして訪問するのは、月に2件のホスピスのみでした。初月の収入は、約2万円。一方Miyabiさんは同時期、友人と共同経営でエステサロンを開業しておりケアビューティストとエステティシャンの仕事を5:5ほどの割合でこなしていました。
「落ち着きがないですよね(笑)。新しいことを勉強するのがもう楽しくて、いろいろなことに興味が湧いちゃうんです。それまで知らなかった知識が頭の中に入ってくるのは、わくわくします」
記憶の中で、楽しかった思い出のほうが上回る
ケアビューティーの施術は、20分と短時間です。施術メニューはメイクやネイルのほかに、リンパドレナージュやフェイス・ヘッドマッサージなどもあります。

「メイクやネイルは、最初は皆さん、恥ずかしいからと薄いお色を選ばれるんですよ。でも、慣れてくると『(家族や周囲に)気づいてほしい』と感じるようで、濃い色に挑戦してくださいます。どの方にも好きなカラーがあって、それは着ているお洋服に表れていることが多いので、お洋服の色はいつもメモしています」
訪問介護と同じように、ケアビューティストの仕事でMiyabiさんが大切にしているのは、「スキンシップ」と「会話」です。認知症を患う人の中には、家族の顔や子どもの名前、自分の産んだ子どもの数すら思い出せない人もいます。それでも、Miyabiさんのことは覚えています。
「思い出がありすぎて、一番は決められないんですけど……」と前置きして、Miyabiさんが、ホスピスでのある忘れられない出来事を教えてくれました。
「60代ぐらいの女性で、首から下が一切動かない寝たきりの方がいらっしゃって。首に管を通されていて声も出しにくい状態だったんですけど、ゆっくり、小さい声なのですがよくお話をしてくださる方で、毎回『真っ赤なネイルを塗ってほしい』っておっしゃるんですね。それで私、失礼を承知しながらも、『ご自身で手を上げられないのに、ネイルをしても見えなくありませんか?』と聞いてみたんです。
すると、ここ(ホスピス)に来る前はね、ずっと自分でネイルを塗っていたから、この姿を見たら娘たちが喜ぶでしょ? って。『弱っていくだけじゃなくて、お洒落もちゃんとしているのよ』という姿を見せたい、ということをおっしゃったんです」
ホスピスはそういう場所——。頭では理解しているにもかかわらず、担当した方が亡くなるたびに、悲しみは込み上げます。それでも、「記憶の中で、楽しかった思い出のほうが上回るんです。やっていて良かったなと、毎回思いますね」と、Miyabiさんは優しい笑顔を見せました。

現在Miyabiさんは、月7件のホスピスや高齢者施設を訪問し、一月あたり50人前後を担当しています。
ケアビューティストの存在はまだ浸透しておらず、現状は、ケアビューティストに資金を回すだけの経済的余裕がある施設からの依頼が大半です。けれどもMiyabiさんは、ゆくゆくはどのような形態の施設でも、誰もが平等にケアビューティーが受けられるようにと願っています。
「介護スタッフや医師・看護師、家族などが集まって介護プランを組むための『担当者会議』というものが、一般的にどの介護施設でも行われるんですね。今、私たちがそこに呼ばれることはありませんが、今後は、ケアビューティストが必ず同席するようにまで認知度を上げていきたいです」
訪問介護時代にMiyabiさんが担当した90代のおじいさんは、余命半年と医師に言われていましたが、Miyabiさんに出会ったことで「楽しみができた」と家事を積極的にやるようになり、2年後の今、杖なしで元気に外を散歩しています。
Miyabiさんが施すケアビューティーには、施術を受けた方の心をストーブのようにじんわりと温め、生きるエネルギーを与える力があるのかもしれません。
(文:原 由希奈 写真提供:Miyabiさん)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。
あなたにおすすめの記事
同じ特集の記事
北海道武蔵女子短期大学英文科卒、在学中に英国Solihull Collegeへ留学。
はたらき方や教育、テクノロジー、絵本など、興味のあることは幅広い。2児の母。
人気記事
北海道武蔵女子短期大学英文科卒、在学中に英国Solihull Collegeへ留学。
はたらき方や教育、テクノロジー、絵本など、興味のあることは幅広い。2児の母。