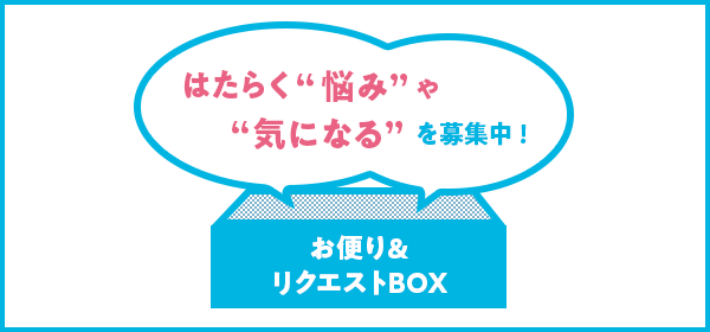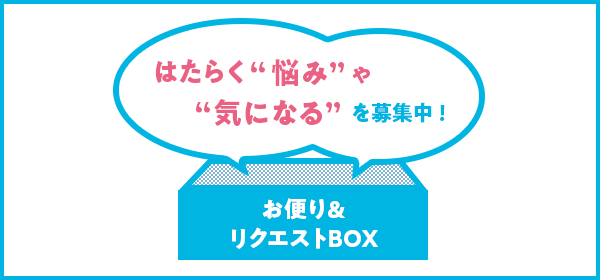- TOP
- サッカー審判員の“はたらく”
- 審判員とは「感動を生み出す仕事」 ─ ジャッジメントの舞台裏 前編 【審判員:家本政明さん】
審判員とは「感動を生み出す仕事」 ─ ジャッジメントの舞台裏 前編 【審判員:家本政明さん】

サッカーの試合において選手の活躍を目にする機会は多いですが、ピッチ上で汗を流しているのは選手だけではありません。試合を冷静にコントロールする審判員の存在があってこそ、すべての試合が成立しています。パーソルグループと日本サッカー協会の共同企画でお届けする「サッカー審判員のはたらく」では、6回に分けてサッカー審判員という職業の実態、裏側、苦労などを解剖していきます。
第2回は「ジャッジメントの舞台裏。選手と対等に渡り合えるコミュニケーションとは」をテーマに、JFAプロフェッショナルレフェリーの家本政明さんにお話を伺いました。(聞き手:日々野真理)
| 審判員: ・家本政明さん プロフェッショナルレフェリー、元国際審判員。2010年にサッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合で日本人初の主審を務める。2016年に国際審判員を引退し、Jリーグなどで引き続き審判員を務める。 ゲスト: ・鈴木啓太さん(元サッカー日本代表・現在 AuB株式会社代表取締役) ・大浦征也(パーソルキャリア株式会社 執行役員・公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル理事) |
「あるべき姿」にはギャップがある
――家本さん、昔と今で、審判員のコミュニケーションの取り方が変わってきていると感じることはありますか?
家本さん:僕が国際審判員になる前は、選手とあまり話をするな、笑うなというのが方針としてありました。自分では「なんでそんなに敵対するのかな?」と思いながら、求められたとおりにするわけですよ。でも、そうすると当然うまくいくわけがない。審判員の中でも「それってどうなんだろうね」という思いがありました。
審判員は笛を吹いて悪さを摘発するような役割ではなくて、一緒にフットボールをつくるため、協働して夢を実現するため、お客さんと一緒に感動を創り上げるために、選手やお客さんと向き合う必要がある。そういった日本に欠けていた価値観を海外から注入してくれるような機会もありました。我々はその中で選手やチーム、メディア、いろいろな方と切磋琢磨しながら変わってきています。

――鈴木さんは選手目線でも審判員とのコミュニケーションが変わってきたのを感じていましたか?
鈴木さん:僕が晩年に審判員とうまくコミュニケーションを取れるようになったのは、自分が柔軟になったのもあるかもしれませんが、もしかしたら審判員の方から歩み寄ってくれるところも出てきたのかなと思います。逆に僕が若いころは、確かに毅然とした態度で「このジャッジはもうこれで正解だから」と言われてしまうと、こっちが何を言っても「NO」みたいな感じになっていたので。

家本さん:審判員が思うあるべき姿と、周りの方が「審判員はこうあるべき」と思うスタイルに多少ギャップがあると思います。付け加えるならば、僕は海外で試合を裁くときのスタイルと国内でのスタイルを変えています。
海外では文化や歴史、考え方が日本と違って、求められるものも違う。なので判定基準を変えるわけではなく、社会や歴史、文化、価値観が変われば、そこに適応することが僕は望ましい姿だと思います。
大浦:ビジネスの世界でいえばダイバーシティマネジメントやグローバルと言ったときに、日本の考え方がそのまま海外では通用しないことが当たり前ですし、言葉が話せても、そのニュアンスや価値観の違いによって必ずしも意思疎通が十分にできるわけではないですからね。

サッカーは「グレー」を楽しむことが大事
大浦:選手との会話だけでなく、監督やコーチ、メディア、ファン・サポーターとのコミュニケーションもあるじゃないですか。みんなにとって100点のジャッジはなかなかないと思います。
家本さん:まずは現場が大事なんです。要はピッチの中が一番。でも、AチームとBチームが一つの判定の内容に対して言いたいことが違うときもあります。同じチームの中でも、たとえば怪我から復帰したばかりだったり、怪我を抱えながら出ていたりして、その試合に集中できていない選手や、結果を出さなければならず舞い上がっている選手とはなかなか冷静に話せない。
そうすると万人に一つの切り口だけではうまくいかなくて、ある選手には直接的でいいかもしれないけれど、別の選手には僕が直接話すよりは、人を介した方がいい場合もあります。あるいはあえてタイミングをずらして、少し冷静なタイミングを見計らった方がいいこともあります。

――選手側からしても、状況に応じてアプローチしてくれた方が自然な形で納得できるのでしょうか。
鈴木さん:毅然とした態度や競技規則が前提としてあるのは当然だとしても、やはりこちら側を向いてくれているかどうかはすごく気になるし、見てくれていると感じられれば協力して一緒にゲームをつくろうと思えます。
僕が浦和レッズでキャプテンをやっているときに、審判員から「チームに落ち着くように言ってくれ」とお願いされることもありました。厳しい判定が出たときは審判員側に立って、僕がチームに落ち着くよう伝えることによって、少し収まることもあります。
ただ、試合は生き物です。それを人がつくってい中で、最近はVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)が出てきました。レフェリーに見えなかったものが機械的に見えるようなテクノロジーによって、コミュニケーションの取り方はどう変わっているのでしょうか。
家本さん:VARに関しては、多くの人が正解を大事にしようとしている価値観が反映されていると思います。サッカーに求められている価値が、昔に比べるとビジネス寄りになってきているところはあると思うんです。街の子どもたちのサッカーにVARはいりませんよね。ただ、求められるレベルが高い世界になると、ビジネス寄りになるのは否めないのかなと。
そもそもサッカーの競技規則自体がすごく曖昧なものなのに、白黒つけたがる傾向がありますよね。だからこそ審判員も、お客さんも、チームやメディアも含めていろいろな人がサッカーを楽しむのであれば「グレーを楽しむこと」が大事だと思っています。モヤモヤしたものはすぐ手離したくなりますけど、ビジネスだってモヤモヤを抱えて、悩んで、押したり引いたりしてみて、待ってみて……とやる中で何かが形になってきたりすると思うんです。それはサッカーの楽しみ方の大きな要素の一つでもあると思っています。

ミスは簡単には忘れられない。新しい自分をつくり出す
――家本さんと鈴木さんは実際にピッチで一緒にお仕事をされたこともあると思いますが、当時の思い出や印象に残っているエピソードはありますか?
鈴木さん:僕、家本さんとうまくやっていた方だと思うんですよ。結構会話してくれるから。
家本さん:鈴木さんは闘争心もありながら頭が良くて、僕との関係性でいうと、すごくポジティブです。困ったら「啓太くんちょっとあのさ、あのときのこと〇〇に言っといてくれる?」「あ、すみません。分かりました!」という会話もありました。すごく信頼できるキャプテンの一人でした。
――主審をされるときに、そのチームのリーダーは誰なのかということも調べるんですか?
家本さん:監督がどれくらい主導権や影響力を持っているのかも当然考えますし、試合でキャプテンマークを巻いている選手が本当にリーダーなのかも調べます。キャプテンマークを巻くのには、いろいろな意味や理由があるじゃないですか。全体を見て、年齢やコンディションも考えて、本当のリーダーはピッチ上の11人の中にいるのか、ベンチにいるのかも確認します。
鈴木さん:家本さんは判定ミスをしてしまったとき、その次のプレーはどうジャッジするんですか? そのときのことはもう忘れて続けるんですか?
家本さん:「忘れたの?」とよく言われるんですけど、そんな簡単に忘れられないですよね。しかも、そのミスが大きければ「やっちゃった、さあどうするかな……」みたいに考えることもあります。
ただ、ミスに自分の心が食われてしまっては、周りの選手や、その試合を楽しみに来ているお客さんや視聴者の方々を無視することになります。なので、悲しい自分は横に置いておいて、また新しい自分をつくり出すイメージでやっています。
まずは割り切るというか。今度は自分の奥にある、本当のフットボールの姿であったり、魅力であったり、楽しさであったり、みんながたどり着きたい喜びや笑顔みたいなところを取り戻せるか、そして自分の姿を消すことに集中します。一度、透明人間になるんです。一秒先に何が起こるかわからないので、今はこういう状況で、こういう温度感になっているから、じゃあこれとこれだけは絶対にやってはいけない、これだけは絶対にミスをしてはいけないと、消すものを消した上で、みんなにもう一度サッカーの世界に戻ってもらうために、自分が何をしなければいけないのかを考えます。
鈴木さん:審判員って、人生の修行のような気がします。白黒つけなくてはいけなくて、機械的にやらなければいけない職業ではあるけれども、根っこは人間臭くないといけないというか。
家本さん:競技規則の表面上の正解・不正解ばかりにとらわれて、周りの期待や喜びを無視していたときもありました。それは大きな失敗で、すごく反省もしたし、じゃあどうしたらいいんだろうということも考えました。その結果、競技規則に書いてある、サッカーを楽しむ、サッカーを通じてみんなでつながる、そういう競技の精神の出発点に戻ってきたんです。

――審判員は試合中に選手を名前で呼ぶのでしょうか?
家本さん:僕は極力、名前で呼びますけど、それは関係性があってこそです。僕は鈴木さんのことを試合中「啓太」と呼んでいたんですけど、ときには「鈴木さん」と呼ぶこともありました。なぜかというと、鈴木さんにも心があるからです。僕に「啓太!」と呼ばれるのを受け入れるタイミングがある一方、気に入らないタイミングもあります。それを感じるのもすごく大事だと思っています。
鈴木さん:信頼関係が生まれてくると、「今は気遣ってくれているんだな」というのも感じられるようになってくるんです。だから僕は家本さんに「啓太」と言われていたのが心地よかったですし、ちゃんと信頼関係を築けているなと感じていました。でも、僕だって主張するときはしますし、それで会話が生まれるんですよ。
――逆に選手から「家本さん」と呼ばれて会話が生まれることもありますか?
家本さん:最近は名前で呼ばれることも増えてきましたけど、まだ「レフェリー!」とか「てめえ!」と言われることも、残念ながらあります。だから、いい意味で選手をイジることもありますよ。「ちょっと聞こえないからもう一回言ってみて」とか、「今、お前って聞こえたんだけど……」とか。
鈴木さん:熱くなっていると、選手もセルフコントロールが効かなくなることがありますからね。審判員は大変だと思いますよ。
家本さん:また、試合だけではなく公共の場で、みんなに見られている中で、どういう表現や接し方、タイミングでコミュニケーションをとるかということも、常に考えています。
厳しいことを言われるのも、人間だから当然「ん?」と思うこともありますけど、僕はその場に「審判・家本 政明」で登場しているので、審判員だから感情的になってはいけないということは、常に自分に言い聞かせてますね。
長いキャリアの中で、反省して、調整して、修正してきた結果、「家本 政明」という、「はたらく人」が出来上がっていくんです。そこにプロとしての価値が見出されて、プロフェッショナルレフェリーとして契約してもらい、大きなお金を投資してもらって、難しい試合を担当させてもらえている。僕本人ではなく、「家本 政明」という審判員に投資してもらっていると思っているので、そこにプライベートはないです。

審判員とは、感動を生み出す仕事
――海外では審判員という職業の社会的な地位は高いですか?
家本さん:ヨーロッパでは非常に高いですよ。弁護士や会計士など、社会的地位の高い方が審判員をされていることも多いです。ただ、日本と海外では背景が違って、たとえばイングランドでは審判員組織が独立しています。そこに対してプレミアリーグをはじめ、いろいろなところがとんでもない額を投資しているんです。そうすると予算規模が大きくなるので、審判員に払える報酬の額も変わってきますよね。
大浦さん:ヨーロッパと日本を単純に比較して、違いを論ずるのは簡単ですけれども、やはり歩んできた歴史も経済規模も違うというのは、おっしゃる通りだと思います。でも、日本も海外から学ぶところはあると思うので、審判員はスポーツが本来持っている感動やエネルギーをつくっていくために、こんな思いを持ってやってきているということが発信されていくと、取り巻く環境が変わってくるんだろうと感じます。
家本さん: Jリーグは社会のどんな問題を解決するのか、どういう価値を創造していくか、この二つは真剣に向き合わなければいけないと思っています。我々審判員も、ただ単に笛を吹いて試合を交通整理のように裁くのではなく、どういう価値を創造しようとしているのかをもっと考えたほうがいいと思うんですよね。
そうすることによって世界に認められ、人、物、金が集まってくる。ビジネスもそうやってスケールアップしていくと思います。何をみんなに届けるか。何をみんなから期待されているのか、ということにもっとみんなが真剣に向き合えば、意識が変わるはずです。その先では、サッカー選手と審判員の関係性や、コミュニケーションをとる際の言葉遣い、向き合い方も当然変わるだろうと思います。
――では最後に、家本さんにとって「審判員としてはたらく」とは。
家本さん:「感動を生み出すこと」ですかね。審判員は競技規則に書かれているように、笛を吹いたりカードを出したり、難しいことがあったら場を整える役割ですが、僕はそれが重要ではないと思っています。
競技規則の前文には、競技の本質を踏まえたうえでレフェリングしなさいよ、と明確に書いてあります。その競技の本質や精神とは何か。人の感動が大きくなれば、より多くの人が集まってくる。より多くの人が集まってくれば、もっと大きな価値が創造されていって、カッコよく言うならば、世界平和になる。みんながいつも笑顔で笑っていて、抱き合って、助け合えるようになる。悲しいこともあるかもしれないし、悔しいこともあるかもしれないですけれども、審判員はそういう心がたくさん動く仕事に携われているのです。なので、それが審判員という仕事なのではないかと思います。
(聞き手:日々野真理 文/写真・舩木渉 写真提供:JFA)
▼本インタビューを動画でご覧になりたい方はこちら

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。