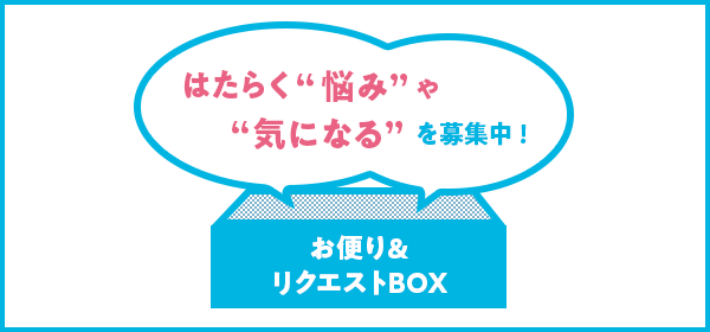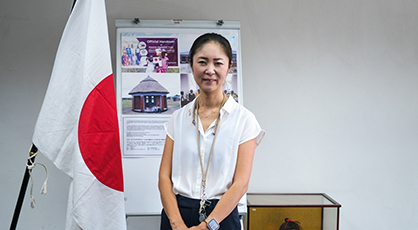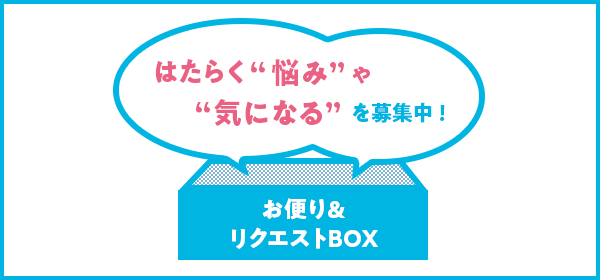- TOP
- サッカー審判員の“はたらく”
- 海外で笛を吹くということ ─ 国際審判員の“はたらく”【審判員:佐藤隆治さん】
海外で笛を吹くということ ─ 国際審判員の“はたらく”【審判員:佐藤隆治さん】


サッカーの試合において選手の活躍を目にする機会は多いですが、ピッチ上で汗を流しているのは選手だけではありません。試合を冷静にコントロールする審判員の存在があってこそ、すべての試合が成立しています。
パーソルグループと日本サッカー協会の共同企画でお届けする「サッカー審判員のはたらく」では、6回に分けてサッカー審判員という職業の実態、裏側、苦労などを解剖していきます。
第4回は「なぜ海外で笛を吹く?外国人と会話できるの?JFA国際審判員のはたらく」をテーマに、JFAプロフェッショナルレフェリーで国際審判員でもある佐藤隆治さんにお話を伺いました。(聞き手:日々野 真理)
| 審判員: ・佐藤隆治さん プロフェッショナルレフェリー、国際審判員(主審)。2009年より国際主審に登録、2018年のワールドカップやクラブワールドカップなどで担当審判員に選出。 ゲスト: ・大浦征也(パーソルキャリア株式会社 執行役員・公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル理事) |
30代から世界の舞台へ挑戦
――まずは、国際審判員となったきっかけを教えてください。
佐藤さん:最初から国際審判員をやりたいというより、まずはJリーグのピッチに立ちたかったのが審判員の世界に入った本当のきっかけです。
現在Jリーグ全体だと約150人の審判員が関わっていて、その中でもJ1で主審として笛を吹いているのが約20人、国際審判員はまた別の資格になります。各国に枠があって、日本から国際主審として登録してもらえる審判員は最大7人です。国際審判員というのも頭の中にはあったんですけれども、なかなかなりたいと言ってなれるものではありません。僕の場合は 2007年からJ1で主審を担当し始めて、翌年の夏に日本サッカー協会から声をかけていただき 、2009年から国際審判員になることができました。

――国際審判員になると、どんな試合を担当することになるのでしょうか。
佐藤さん:アジアだとAFCカップやAFCチャンピオンズリーグ、そしてワールドカップ予選などがあります。海外の公式戦を裁くためには、国際審判員の資格が必要になります。
――担当する試合にかかる責任は非常に重いですね。
佐藤さん:国際審判員になって今年で13年目になりますけれども、やればやるほど責任の重さや、1試合の大きさ、インパクトをひしひしと感じています。2009年に国際審判員になったばかりのころは、今考えると本当に甘かったなと思います。
大浦:今年で13年目ということは、30歳くらいで国際的な舞台で笛を吹くことになったわけですよね。一般的なビジネスの世界では、30歳で海外に出ていくのはむしろ遅いくらいかもしれない印象があります。ただ、30歳の審判員にとっては自分より年上の選手もいると思うので、国際試合で笛を吹くようになるには早いのではないかと感じたのですが……。

佐藤さん:日本人で国際審判員になるのは30歳前後が多いと思いますけれども、海外ではもっと早いです。30代半ばでワールドカップに出てくる審判員もいるので。ただ、僕らは世界との勝負、競争になるので、最近は多少経験が少なくても若くて活きのいい審判員を国際舞台で活動させる流れになってきています。
大浦:審判員は試合をコントロールする、ビジネスの世界でいうとマネジメントの立場であると考えると、海外ではJリーグで笛を吹くのとはまったく違った難しさがあると思います。また、30歳でグローバルな舞台で試合をマネジメントするのにも、別の難しさがあるのではないでしょうか。
佐藤さん:多いときは1試合に6人の審判団で臨むのですが、主審が一番若いことも起こり得ます。やはり日本人だと先輩・後輩など、いろいろありますよね。でも、ピッチに立てば主審がボスなので、主審がどれだけリーダーシップを取っていけるかが重要です。任された役目を果たすという意味では、若くして海外に出ていくには、キャリアの多少に関わらずリーダーとして審判団を引っ張っていける能力が求められるのではないかと思っています。
僕がJ1で笛を吹き始めたころ、自分が一番若くて、両副審にベテランの方がついてくださって心強い部分もありました。でも、少なからず遠慮してしまう部分もあって難しかったです。それは海外でも最初は同じでしたけど、国際審判員を13年やらせてもらっていて、国内でやっているのと海外でやっているのと、普段の仕事に違いはほぼなくなりました。
あとは複数のチームが一箇所に集まって試合をする国際大会になると、必ずしも日本人だけで審判団を組める試合ばかりではないんです。多国籍軍で審判団をつくるときに、仮に自分より年上の審判員と一緒であっても、リスペクトは持ちつつ、自分がリーダーとして、いかに周りの審判員をまとめていけるかが重要だと、これまでの経験を通して学んできました。

短期間で意思疎通を図る国際審判員
――国が違えば、レフェリングの仕方や判定基準の違いが当然あると思います。それはどうやって同じ方向にまとめていくのでしょうか。
佐藤さん:世界共通のスポーツで、同じ競技規則でやっているんですけれども、やはり国や地域によって、競技規則の解釈に違いはあると思います。それを試合前にコミュニケーションをとって、話をして、同じベクトルに向けていかなければなりません。そうしなければ、試合がうまく進んでいかないのだと、国際審判員の経験を通して学ばせてもらいました。
最初は必要以上に介入して、僕が必要としていないことにまで首を突っ込んでくることもあります。それは向こうも良かれと思ってやってくれているので、僕が「ありがとう」と言えば、またやります。なので、それに対して「僕はこう考えているから、こうしてほしい」ということを言わないと、向こうはこちらが何を欲しているのか、要求しているのかが分からないんです。
大浦:「はじめまして」の審判員はどんなジャッジをするのかわからないと思うのですが、国際試合では事前に顔合わせする場が設けられるのでしょうか。
佐藤さん:コロナ禍で現在は少し変わっていますが、通常は試合の2日前に入国するのが国際試合のルールで、試合翌日に帰国するまでが1つのサイクルです。
そうすると入国してから試合までの2日間がすごく大事になります。僕たちは同じホテルで生活するので、食事をしながら「あなたは誰?」「どこからきたの?」という会話から初めて、試合の動画を見ながらディスカッションするようになり、「僕はこうしたいから、こういうサポートをしてほしい」といった話をしていきます。
2日間ではそのくらいしかできないので、本当に「はじめまして」から試合をするときは、サポートをお願いすることに優先順位をつけます。主審がしっかりマネジメントしていかないと、「やってくれると思っていた」という思い込みで試合に入ってしまって、うまくいかないのが一番マズいので。
日本と海外では何が違うのか?
――国際大会では試合中に何語を喋っていらっしゃるんですか?
佐藤さん:「国際審判員をやっています」と言うと、よく聞かれる質問です。僕らが普段担当するアジア地域は国の数が多く、それぞれ言語もまったく違います。そのため英語がコミュニケーションをとるためのツールになりますが、そんなにペラペラ喋れるわけではありません。
ただ、試合中に主語、述語、目的語の揃ったきれいな英語を喋る必要があるかといったら、そうではない。選手はアドレナリン全開で、感情を爆発させながらプレーしていて、僕らもプレッシャーのある環境で試合を裁いています。なので、きれいに喋ることよりも、どれだけ自分の意思を伝えられるかが重要です。
たとえばファウルが多い選手に、なんとかやめさせたいなら「ネクスト!イエローカード!」と言って、「もうマズいんだ、警告されているんだ」と伝わればいい。英語が伝わらないケースもあるので、そういうときはジェスチャーや表情、声の強さでもよくて、とにかく大事なのは審判員の意思をどんな形であれ相手に伝えることです。

大浦:国際審判員になるとき、英語などの語学力の基準はないんですか?
佐藤さん:特に何か課せられていることはないですけれども、海外の試合やセミナーに行けば英語でディスカッションすることになります。映像を見て、英語で自分の意見を言わなければいけない。なので、まったく喋れないのはマズいですね。僕も審判の世界に入って、Jリーグを吹くようになって、チャンスがあれば国際審判員になりたいなと思うようになってから、昔の教科書や参考書を開いて少しずつ勉強してきました。
英語は喋れないより喋れた方が絶対にいいです。でも、喋ることと、どうやってコミュニケーションをとって意思を伝えていくかは別物というか、どちらかが良ければいいというわけではないと思っています。やはり英語を流暢に喋れて、なおかつその場の状況に応じて意思を伝える能力があることが一番いいと思っています。
――審判員の見られ方は日本と海外で違いますか?
佐藤さん:それは大きく違うと思います。やはり海外で笛を吹くときの方が、サッカーの国際審判員はすごい立場なんだなと感じます。国によっては、飛行機が到着したところからまったく並ばず「どうぞ」と手続きが進み、荷物まで全部出してもらえていることもあります。入国管理官に審判員として名前を知られていることもありました。
おそらくサッカーの審判員に対する考え方が、日本と違うんだなというのは、よく感じます。社会的地位の高低ではなく、興味を持ってもらえている感じがするんです。審判員も、みんなが大好きなサッカーの一部という感覚なんだと思います。
――海外に行くと、自分の想像をはるかに越えるようなことが絶対にありますよね。
佐藤さん:ありますね。国際審判員になりたてのころはいろいろなことにすごく敏感になっていて、ホテルが……、食事が……、気候が……と、よく不満を言っていました。でも、国際主審のワッペンをつけている以上、当然日本と海外は違うわけで、まずその違いを受け入れなければいけません。僕は「やってくれ」と言われて国際主審になったわけではなく、やりたいからやらせてもらっているので、自分のマインドを変えて、文化や食事などすべての違いをとにかく受け入れる。そうやって自分が変わっていかなければ、続かないと思いました。
大浦:違いを違いとして受け入れるだけではなく、違いがあるからこそ、お互い学び合うことも必要なのではないかと思います。レフェリングや試合のマネジメントにおいて日本人の審判員が秀でていると感じるところや、逆に日本が国際社会から学ばなければいけないと感じるところを教えてください。

佐藤さん:やはり日本人の特徴は、勤勉さや正確さだと思います。1試合で100回以上、ファウルかどうか見極めるタイミングがありますけれども、それをすべてきちんとやろうとするのが日本人です。審判員だけでなく、選手も、スタッフも、メディアも、ファン・サポーターもすべての判定の正しさに重きを置きます。僕らはそういう環境で育ってきているので、一つひとつの判定にきちんと向き合う能力は、他国の審判員に比べて非常に高いと思います。
ただ、正確に判定することも大事ではありながら、判定にも優先順位があって「ここは絶対に落としてはダメ」というところさえ失敗しなければ、あとは多少のミスがあっても話題にはならないと海外で笛を吹いてみて気づきました。
確かに一つひとつの判断の積み重ねによって試合をコントロールするのですが、僕たちは99個の判定が正しくとも、残りの1個で大きなミスをしてしまったら、それで終わりなんです。海外でどんな審判員が高く評価されているかを見てみると、正確性が必ずしも最重要項目ではありません。特にヨーロッパの審判員は、試合の流れの中で落としてはいけない判定をきちんと拾って裁いていくのがうまいですね。
細かく見て「え!?」と思うような判定があっても、大局的に見たらしっかりとマネジメントされている。状況に応じて対応を変えながら、選手たちを自分のコントロール下に置いていく。彼らは感覚的にやっているのかもしれませんが、ヨーロッパの審判員を見ていてすごいと思うのはそういうところです。

――日本と海外ではミスをしたときのバッシングのされ方に違いはありますか?
佐藤さん:どちらでもバッシングは受けます。ただ、1試合に対してとなると、日本の方が多いかもしれないです。国際試合では一瞬温度が上がるんですけれども、試合は流れていくので、次に進んでくれるというか、過去のことをしつこくは言ってきません。
ただ、試合の結果に影響するようなミスをしたときは国内でも海外でもバッシングを受けますし、場合によっては何年も前のことであっても忘れてくれないこともあります。海外は、好意的なこともネガティブなこともダイレクトに伝えてくれるので、僕は性格的に本当は嫌いなのに好きと言われるより、嫌いなら嫌いと言われる方がいいですね。
言い訳なしに自分と向き合う
大浦:選手は現役時代のハイライトになる1試合を挙げてくださいと言われたら、いろいろ出てくると思いますが、審判員にとっても忘れられない試合はありますか?
佐藤さん:名だたる決勝戦も担当させてもらいましたし、その景色も、どんな気持ちだったかも自分の中に残っていますけれども、より鮮明に覚えているのはやはり大きなミスをした試合です。そういう試合のことを、僕は死ぬまで忘れないと思います。
その時の自分の心境、選手のリアクションや表情、サポーターがどんな熱量だったか、すべてが鮮明に記憶に残っています。でも、失敗ばかり覚えていても、ネガティブには捉えていません。もちろん審判員のミスはみんなにとって不幸なものです。僕もできるなら避けたかった。
とはいえ選手やチームにうまくいったこと、うまくいかなかったことの両方があるのと同じで、審判員にもそういったものはありますし、すべてが次につながっているのは間違いありません。大きなミスをした試合のあと、歯がゆい気持ちになって、ものすごく悩むのは僕だけではないと思います。審判員は、それがあるから「次の試合こそは」という気持ちでやれるのだと思います。
――たくさんのお話を伺ってきましたが、最後に佐藤さんにとって「審判員としてはたらく」とは。
佐藤さん:やはり自分と向き合うことです。AチームとBチームがやれば、どちらかが勝って、どちらかが負けるのが、スポーツの運命ですよね。みんながハッピーになれることはないと思います。それを僕らが裁いているわけですけれども、僕らに勝ち負けはなく、大事なのは自分がやるべきことをきちんとやりきれたかどうか。どんな試合でも、終わってから振り返れば少なからず改善点が出てきます。
ミスが大きければ大きいほどバッシングにもつながりますけれども、それを受けなかったからいいというわけではなく、選手やファン・サポーターなどからの反応は一度横に置いておいて、その試合で何がよくて、何が悪かったのか、きちんと言い訳なしに自分と向き合うことが必要です。それが僕にとって「審判員としてはたらく」ということであり、自分と向き合い続けていかなければ、今のポジションにはいられないのかなと思います。
(聞き手:日々野真理 文/写真・舩木渉 写真提供:JFA)
▼本インタビューを動画でご覧になりたい方はこちら

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。