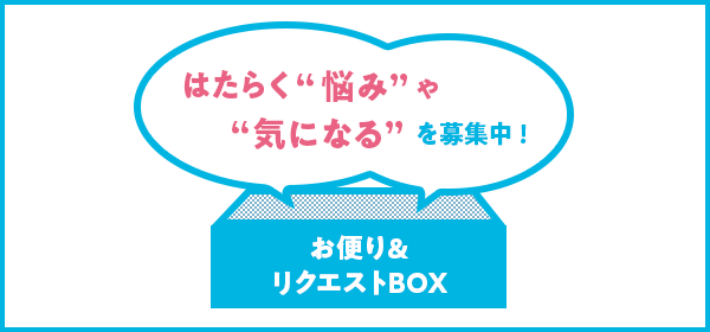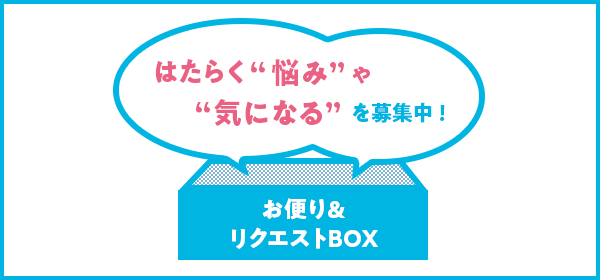- TOP
- WORK LIFE THEATER
- 元DJ世界チャンピオンのCO-MAがいつのまにか農業にハマり、日本一になった話
元DJ世界チャンピオンのCO-MAがいつのまにか農業にハマり、日本一になった話

DJで世界を制し、米農家として日本一に
2006年9月10日、ウエスト・ロンドン。1919年にオープンし、ローリング・ストーンズ、セックス・ピストルズ、U2などもライブをしたことで知られる老舗クラブ「ハマースミス・パレス」で、世界一のDJを決める大会「DMC WORLD DJ CHAMPIONSHIPS」の決勝戦が行われました。
その舞台に立ったのは、DJ CO-MAこと駒形宏伸さん。フランス人のDJと対戦した駒形さんがプレイを終えた瞬間、満員の観衆からヒューッ!という無数の口笛、万雷の拍手と歓声が贈られ、ハマースミス・パレスの盛り上がりは最高潮に。
この日、DJ世界一の栄冠を手にした駒形さんは、その4日後には、新潟の南魚沼にある田んぼで稲刈りをしていました。一息つこうと視線を上げると、越後三山が目に入ります。どこからか吹いてきたそよ風を感じながら、駒形さんはウエスト・ロンドンでの夢のような一夜に思いを馳せました。
それからしばらく時が流れ、2020年12月18日に静岡県磐田市で開催された、お米の食味コンテストとしては国内最大級の「第17回お米日本一コンテスト」に出場。コロナ禍により無観客開催となったこの日、駒形さんは南魚沼の自宅で大会事務局からの連絡を受けました。結果は、最高金賞。全国から597点がエントリーしたこのコンテストで、最高金賞に選ばれたトップ5の一人として名を連ねたのです。
DJで世界を制し、米農家として日本一に選ばれたのは、世界広しと言えども駒形さんしかいないでしょう。その人生は、「探究」の道のりでした。
後継ぎ扱いがイヤで仕方なかった少年時代
1979年、駒形さんは江戸時代から南魚沼でお米を作ってきた農家の長男として生まれました。四人きょうだいの末っ子で、上には3人の姉。必然的に、子どものころから「後継ぎ」を意識して育ったそうです。

「親父は好きなことをやれと言っていたけど、ちょいちょい『農業が一番いい』と聞かされていました。近所のおじいちゃんからも『農業はいいぞ、お前はいずれ継ぐんだ』と言われていましたね」
駒形少年は、それがイヤでイヤで仕方ありませんでした。着古したジャージ姿で、いつも泥だらけになって農作業をしている自分の父親を恥ずかしく感じ、ネクタイを締めてスーツで仕事に行く同級生の父親たちが眩しく見えました。
「農業なんて……」と拒否感を持ったまま育った駒形さんはやがて、「陸上部がある会社に入って、そこで競技を続けられないか」と考えるようになっていました。子どものころから足が速く、中学時代に110メートルハードルで全国大会に出場してから、高校、大学とスポーツ推薦で進学していたのです。しかし金沢工業大学3年生の時、コーチの一言で陸上競技への想いが一気に冷めました。

「大学に入ってから伸び悩んでいたんですが、自分なりに真剣に取り組んでいました。でも、ある日コーチから『お前の身長じゃ限界がある』と言われたんですよ。すごいショックで、次の日から部活に行かなくなりました」
服と家具を売って購入したターンテーブル
そのころ、電撃的な出会いが訪れます。お酒を飲もうとアルバイト仲間の家を訪ねたら、その部屋にDJが使うターンテーブルが置かれていました。駒形さんはターンテーブルの存在こそ知っていましたが、実物を見るのは初めてです。その友人がオーディオの再生ボタンを押すと流れてきたのは、宇多田ヒカルの『Automatic』。友人はおもむろに、その曲の冒頭、「デュクデュクデュクデュク」と始まる部分をターンテーブルで再現しました。その姿を見て、駒形さんは直感したのです。
「これだ!」
翌日、駒形さんはお気に入りの服や家具をできる限り売り払い、7万円を得ました。それを持って金沢市内の島村楽器に行き、不足分をローンにして12万円のターンテーブルを購入。その時に世界的DJコンテスト「DMC WORLD DJ CHAMPIONSHIPS」のビデオも購入し、見よう見まねで練習を始めました。
最初のころは、「R&Bの曲をミックスして作ったカセットテープを車で聞ければいいや」程度の軽い気持ちでした。しかし、DJをしていた大学の同級生と仲良くなり、彼らと一緒に海外の大会のビデオやレクチャービデオを何本も観てマネしているうちに、「もっと上手くなりたい」という気持ちが溢れ出て、練習時間が伸びていきました。
DJの技術に「スクラッチ」というものがあります。直訳すれば擦る、削るという意味で、ターンテーブルに載せたレコードを前後に擦ると、たとえば駒形さんが友人宅で聞いた『Automatic』の「デュクデュクデュクデュク」という音になります。スクラッチをしながら、DJミキサーについているフェーダーというつまみを左右に動かすことでいろいろな表現ができるようになるのですが、トップクラスのDJは指の動きが見えないレベルです。
このスクラッチに憧れた駒形さんは無我夢中で練習するようになり、気付けば10時間経っていた日もあったとか。もしかすると、中学生の時から心血を注いできた陸上から離れてポッカリと空いた穴を埋めようとしていたのかもしれません。ただ、当時はあくまで趣味の領域で、仲間内で練習の成果を披露する以外は誰に見せるでもなく、黙々と自室で指を動かしていました。
初めての大会でベスト8進出
学生時代に仕事としてやりたいことが見つけられなかった駒形さんは、大学卒業後、実家に戻りました。思いつきで警察官と消防士の試験を受けるも、筆記試験で落選。次に新潟市内のスポーツショップでアルバイトを始めたもののピンとこないまま半年ほどで退職。いつまでも無職でブラブラしているわけにもいかず、残された選択肢は一つしかありませんでした。
「親父から、やりたいことがないなら農業やってみないか?やりたいことが見つかるまでの間でもいいからって言われたんですよ。初任給20万円で雨が降ったら休みだぞって。その時、レコード買うにもお金が必要だし、もう農業するしかねえかなと思って腹をくくりました」

2001年、24歳でしぶしぶ就農。蓋を開けてみれば手取り6万円、雨の日も当たり前のように仕事があり、「詐欺レベルに騙されました」と駒形さんは苦笑します。当時の駒形さんにとって農作業は予想以上にハードで、何一つ面白みを感じられず、「ただつらくて、だるくて、本当にイヤだった」そうです。
この苦痛から逃れるかのように、駒形さんは仕事の傍らDJの練習に打ち込みました。15分休憩があれば、走って帰宅し、5分でも練習。昼休みも自宅で昼食をすぐに済ませて、残りの時間は練習。仕事が終わった後は、風呂に入って夕食を食べてから、夜中の2時、3時まで練習です。
迎えた2003年、歴史あるDJコンテストITF(International Turntablist Federation)の日本大会にエントリー。圧倒的な練習量で臨んだ駒形さんは、初出場にしてベスト8に進出します。この成績に手ごたえを得ると、さらに練習時間を増やました。農作業は休むことができないので、夜の時間を練習にあて、毎日、2、3時間しか寝ませんでした。
父親は、DJに没頭する息子を苦々しく思っていたようです。夜中に練習をしていると、「今、何時だと思ってんだ!」と怒鳴られ、何度も「(DJを)やめろ」と言われました。それでも駒形さんは意に介さず、スクラッチの技術を磨き続けました。
農業とDJの二足のわらじ
その成果はすぐに表れました。2004年、今度はDMCの日本大会でファイナルに進出し、翌年には優勝。さらに各国の大会の優勝者が集う世界大会では、ベスト8に入ったのです。世界を知ったことで、駒形さんのやる気はさらにヒートアップしました。
「オーディエンスがめちゃくちゃ率直で、パフォーマンスが気に入ればドカーンッて盛り上がるし、気に入らなければ容赦無くブーイングされる。それが衝撃的で、超楽しい!と思ったんですよね。初めての世界大会では3回戦でアメリカ人に負けたんですけど、アメリカ人勝利という判定が出た瞬間に会場が大ブーイングになったんです。オーディエンスが支持していることを感じて勇気をもらい、来年は絶対に優勝してやるっていう気持ちにはなりました」
その言葉通り、日本大会を2連覇した駒形さんは、世界大会でも決勝まで駆け上がります。そして、冒頭に記した通り、ウエスト・ロンドンの老舗クラブ「ハマースミス・パレス」で世界の頂点に立ったのです。

DMCの世界大会ともなると、出場するDJのほぼ全員がプロで、唯一の例外が駒形さん。プロになろうと思わなかったのでしょうか?
「思いましたよ。日本も世界も、大会にはイベント関係者がたくさんくるから、アフターパーティーは仕事をもらうチャンスにつながるんです。でも、日本だと大会やイベントが夏か秋に多いんですよ。そうなると夏はスイカの収穫期、秋は稲刈りとモロ被りするから、いつも大会が終わるととんぼ返りで、アフターパーティーにも出られなくて、もどかしかったですね」
どんなに睡眠時間を削って練習しても、世界大会で優勝してDJ界で有名人になっても、駒形さんは米農家の仕事をさぼりませんでした。それは、次第に駒形家の10代目として後を継ぐ自覚が芽生えてきただけでなく、農業に楽しさを感じるようになっていたからです。

「農作業で疲れた時にふと立ち上がると、目の前に越後三山が見えるんですよ。そこからそよ風が吹いてきた時に『ああ、気持ちいいなぁ』と感じるようになりました。それに、稲刈りや田植えは地域の人たちが手伝ってくれるんですけど、田植えの後にも、稲刈りの後にも慰労会があって、そこでみんなで酒を飲みながらワイワイ話をするのも楽しくなってきたんですよね。だから、このころには農業とDJの二足のわらじで続けていければいいなと思っていました」
アジア人初の世界王者に
DMC世界大会を制した駒形さんが次に目指したのは、もう一度世界王者になることでした。2006年に駒形さんが勝ったのは、バトル部門。一対一のトーナメント形式で、1分半のパフォーマンスを交互に2回ずつ披露して(駒形さんが参加当時のルール)、技術と観客の盛り上がりを競います。
DMCにはもうひとつ、「シングル」という部門があります。こちらは決勝に進んだ複数人が1人6分間のパフォーマンスをして、その中から一人が王者に選ばれます。駒形さんによると、DMCではシングルが花形とされているそうです。
2007年に一度大会から退いた駒形さんですが、次第に「シングル部門も獲りたい」という気持ちが湧き上がってきて、2008年に復帰。それから4年連続で、DMC世界大会のシングル部門に出場しました。結果は3位、2位、2位、3位。どうしてもシングル部門の頂点には手が届きませでした。
その悔しさをぶつけるように、2009年にポーランドで行われた別団体の世界大会「IDA WORLD FINAL」では、初出場にしてアジア人初の世界王者に輝きました。これで、DMCバトル部門と合わせて、世界大会2冠です。このころには世界トップレベルのDJとして名を馳せていた駒形さんですが、あれだけ燃えたぎっていた情熱の炎はいつのころからか小さくなっていました。
「世界大会に行くといつも楽しかったんですけど、2010、11年のDMCの時は楽しめませんでした。そのころから優勝しなきゃいけないっていう変な使命感が出てきてしまって、めちゃめちゃ緊張するようになっちゃって。楽しいより、苦しい、つらいという気持ちになってしまっていましたね」
「松永くん」の上京で気づいたこと

DJから離れることを決めたのは、2012年。その数年前から、駒形さんは農閑期の冬にDJスクールを開いていました。スクールを開くと告知した時、最初に連絡をしてきたのが、現在ヒップホップユニットCreepy NutsのDJとして活躍する、高校時代の「松永くん」です。スクールの初日、横殴りの雪が降っていて、「こんな日に誰も来ないだろう」と思っていたら、松永くんが一人だけ短パンにサンダル、ダウンジャケットという奇妙な出で立ちで現れ、「すっごい変態か天才が来た」と思ったとか。
20人ほどが通っていたDJスクールでも松永くんのやる気と吸収力は頭一つ抜け出ていて、スクールに通い始めて1年を過ぎるころには教えることがなくなったため、「あとは自分で頑張れ」と伝えました。その後も松永くんは、駒形さんに自分で作った演目の感想を聞いたり、相談をしていたそうです。
そして2012年、駒形さんのもとを訪ねてきた松永くんは「俺、東京でやろうと思います」と告げました。その時、「おおそうなんだ、頑張って」と笑顔で応じた駒形さんは、自分の変化に気付いたのです。
「僕の気持ちがDJとして現役だったら、上京するって聞いたらすごく悔しかったと思うんです。でも、本当に素直に応援できたので、この時に『俺もこれからまたほかに熱くなれるものを探さなきゃな』と思いました」
その後、松永くんはCreepy NutsのDJ松永として活躍するようになり、2019年には駒形さんと同じDMC世界大会のバトル部門で優勝。師匠と肩を並べました。
「これはちょっと、負けてらんねえな」
次の「熱くなれるもの」は、意外なほどすぐに見つかりました。松永くんが上京したその年に駒形さんは結婚し、「生活もあるし、そろそろ農業に本腰入れようか」と考え始めていました。そんな時、父親から「楽しいから参加してみたら?」と言われ、農業をしている若手の飲み会に顔を出した駒形さんは、愕然とします。
「自分も10年以上、農業をやってきたからそれなりの知識はあると思ったんだけど、そこにいた人たちはぜんぜん僕とレベルが違いました。話しているのが、僕の知らないことだらけで。みんなちゃんとやってるんだ、俺みたいにちゃらんぽらんじゃないんだって恥ずかしくなりましたね」
この時、農業への想いが、メラメラと燃え始めました。
「これはちょっと、負けてらんねえな」
スイッチが入った駒形さんは、父親にイチから教わるだけでなく、若手の生産者を訪ねて「俺、ぜんぜんわかんねえから教えてくれ」と頭を下げました。DJを始めたころのように、ひたすらどん欲に知識を吸収していきました。
農業は「ミスしたからやり直す」ということができない仕事です。たとえば、スイカの場合、成果を確認できるのは年に一度。その一度の時期を目指して最高のクオリティのものを作るために、生産者は工夫を重ね、手を尽くします。その姿勢から学んだ駒形さんは、昔ながらの育て方、最新の手法、父親の経験と知恵、ほかの生産者のこだわりなどすべてを自分の中に取り込み、スイカと向きあいました。

米作りの師匠との出会い
米作りも、生産者を訪ね歩くところから始まりました。なかには、1777年(安永7年)から続くコメ農家の10代目から教えを請われて、戸惑った人もいるかもしれません。しかし、駒形さんは気にしませんでした。
「まったく抵抗ないですね。むしろ、ガンガン聞こうと思っていました。米の作り方を検索しても、教科書通りのことしかネットには載っていません。おいしいお米の作り方は各農家それぞれが隠し持っているので、なかなか簡単には聞けません。でも本気度が伝わると、包み隠さず教えてくれたりするんですよ」
教えを請うた中に、駒形さんが「レジェンド」と称する、元プロスノーボーダーで、今はコメ農家を継ぎ、さまざまな米のコンクールで受賞を重ねている生産者がいます。駒形さんは、師匠と慕うその生産者のもとに通い詰め、土づくりから学びました。目指したのは、師匠と同じように米のコンクールでトップに立つことです。

「僕はDJをやっていたころから、賞レースが好きなんです。人に評価してもらうことが自分のモチベーションにつながるんですよね」
目標を持った時のすさまじい馬力は、DJ時代からもうかがえるでしょう。寝ても覚めても米のことが頭から離れなくなり、いつしか「飲み会に行っても、米の話ばかり(笑)」になっていました。
その想いが実ったのが、2020年の「第17回お米日本一コンテスト」。全国から597点がエントリーしたコンテストで最高金賞を受賞したのは、冒頭に記した通りです。どんな米作りをして、目標を達成したのでしょうか?
「一番大きいのは、肥料を自分で作ったことですね。自分の家で採れた米ぬかに魚カスや蟹殻、油粕などを混ぜて、それにEM菌と言われる有用微生物群の活性液を混ぜながら撹拌した後、容器に入れて一年以上寝かせます。最初は独学で本を読んだりして作っていたんですけど、師匠からアドバイスをもらって完成しました。これを使うと味にパンチが効いて、化学肥料を使った時とはまったく違うお米ができます」
師匠の背中を追って次の目標へ
この最高金賞を機に、駒形さんは株式会社こまがた農園という名称で法人化し、米をブランド化。今ではミシュラン星付きのレストランで駒形農園の米が使われています。
しかし、DJの時と同じく一度最高金賞を取って満足する駒形さんではありません。日本には大きな米のコンクールが3つあり、今はまだそのうちの一つで受賞したに過ぎないのです。次に狙いを定めているのは、「米・食味分析鑑定コンクール」。
「DJの大会でいうとDMCが日本で最高の大会なんですけど、僕にとって米・食味分析鑑定コンクールはDMC的な存在です。国際総合部門という一番花形の部門があって、今度はそこで金賞を獲りたいですね」
2021年の同コンクールは5000件を超える応募があり、最終審査へ進んだのが42件。この狭き門を越えて駒形さんは最終審査に進んだものの、金賞の次点にあたる特別優秀賞にとどまりました。ちなみに、このとき駒形さんの師匠は金賞を受賞。駒形さんは師匠の背中を追って、今年も金賞を目指します。

最後に、若いころは嫌がっていた農業ですが、今はどう感じていますか?と尋ねると、駒形さんは朗らかに笑い言いました。
「いやー、農業をこんなに好きになるとは思わなかったですね。今、すごく楽しいです。農業をやっていて、良かったな」

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。
あなたにおすすめの記事
同じ特集の記事
近著に『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(2019)、『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(2020)。
人気記事
近著に『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(2019)、『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(2020)。